私が初めてウサギの「ちょこ」と暮らし始めた日、リビングの隅で静かにくつろいでいた彼女が、私の気配を感じて突然こちらを振り向いた事に驚きました。「どうして見えているの?」と不思議に思い、調べてみると、ウサギの目には私たち人間とは全く違う特徴があることを知りました。
この経験から、ウサギの目の秘密や日々のケアについて深く学ぶようになりました。この記事では、特徴的なウサギの目や、その健康を守るためにできるケアのコツをご紹介します。
1.ウサギの視界はどのぐらい?
ウサギと一緒に暮らしていると、「えっ、今なんで気づいたの?」と驚かされる場面がたくさんあります。わが家の「らむね」も例外ではありません。
たとえば私が廊下から見えるリビングを横切ると、廊下の向こう側でくつろいでいたはずの「らむね」が、パッとこちらに顔を向け、走ってくるのです。最初は「偶然かな?」と思っていましたが、毎回同じタイミングで反応する「らむね」を見て、気になって調べてみました。
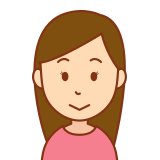
ウサギは左右に大きく飛び出している目をもっており、なんとほぼ360度見えていると知ったのです。
「らむね」のような飼いウサギではない、自然界に住んでいるウサギは、敵から身を守るため、目が発達していたのです。我が家のウサギの普段のおっとりした姿からは想像できない、サバイバル本能の名残を感じます。
2.ほぼ360度の視界を持つウサギ!でも死角もある?
ある日、「らむね」にお気に入りのドライフルーツを正面から差し出したのですが、全く気付かずにキョトンとしていました。そこで、手を少しだけ右側にずらしてみると、すぐに反応して鼻をヒクヒクさせながら近づいてきました。その瞬間、「ウサギには正面に死角がある」という知識が実体験として腑に落ちたのです。以降、おやつやおもちゃを渡す時は、必ず少し横から見せるようにしています。
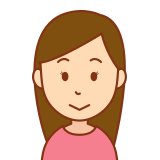
ウサギの視界は広いのですが、実は真正面とあごの下には死角があります。これも実際に一緒に暮らしてみるとよくわかりました。
この「見えている角度」と「見えにくい角度」を意識すると、ウサギとのコミュニケーションがもっとスムーズになります。ウサギの目の秘密を知ることは、心を通わせる第一歩なんですね。
【体験談】「見えている角度」を意識して、「ちょこ」との距離がぐっと縮まった話
最初の頃、私は「ちょこ」の背後からそっと撫でようとしては、毎回驚かせてしまい、すぐに逃げられていました。そのたびに「どうしてこんなに警戒するんだろう?」と悩みました
そんなとき、「ウサギはよく見える角度と見えにくい角度がある」という情報を知りました。
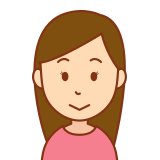
ウサギの大きな目は顔の左右についていて、ほぼ360度を見渡せる一方で、真正面と真後ろは死角になりやすいというのです。
見えにくい角度から突然触ろうとすると、「敵かも!」と感じてびっくりしてしまう——そんな「ちょこ」の気持ちに、私はこれまで気づけていなかったのだと思いました。
それを知ってから、私は「ちょこ」の「視界」に入るように意識を変えました。「ちょこ」の正面や真後ろから手を出すのではなく、少し横からゆっくり近づき、「ここにいるよ」と優しく声をかけるようにしました。
最初はおそるおそるでしたが、次第に彼女もリラックスしてくれるようになり、今では足元で安心して眠る姿を見せてくれるまでに。ウサギの目線に立つことが、信頼関係を築くカギだと実感しました。
今では、我が家のウサギたちのリラックスポーズ(うとうとしながらお腹を見せるポーズ)を間近で見られるようになりました。あの頃のぎこちない関係が、今では信頼に変わったことを、毎日のふれあいで感じています。

3.ウサギの目は動きに敏感、でも視力は弱め?
ある日、私は「らむね」の好きなおもちゃを遠くの棚に置きました。数時間後に見てみると、「らむね」はそのおもちゃにまったく興味を示さない様子。しかし、私がちょっとだけおもちゃを動かした途端、「らむね」はビュンっと飛びついてきました。
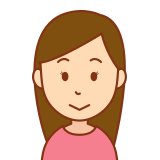
ウサギは、動いているものへの反応は早いのですが、じっとしているものには気づきにくい性質を持っています。
これは、視力があまり強くないためだといわれています。私はその時、ウサギがいかに「動いているもの」に反応しやすいかを実感しました。
【体験談】ウサギが色をどう見ているのかについて
ある日、真っ赤なボールのおもちゃを買ってきて、「ちょこ」の前に転がしてみたのですが、思ったほど反応してくれませんでした。興味を示すどころか、まるでそこに何もないかのような態度で、私はちょっとがっかりしてしまいました。
「もしかして気に入らなかったのかな?」と思いながら調べてみたところ、
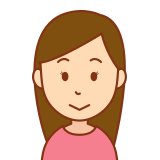
ウサギは青や緑は認識できるけれど、赤はあまりわからないらしいということを知りました。
そこで改めて、鮮やかな青色のボールを選んで「ちょこ」に見せてみたところ、今度は興味津々!鼻先でツンツンしたり、前足でちょいちょい転がしたりして、すぐに遊び始めたのです。
この経験から、ウサギが見やすい色を意識してあげることも、コミュニケーションを深めるコツだと感じるようになりました。ウサギのおもちゃやグッズを選ぶときは、なるべく青や緑を意識して選ぶようにしています。
ウサギにとって「見える世界」を少しでも理解しようとすることが、心を通わせる第一歩なのかもしれません。
4.換毛期は要注意!ウサギの目に毛が入りやすい
換毛期になると、朝起きた時にケージの中がふわふわの毛だらけになっていることがよくあります。ある年の春、「らむね」が片目をしきりに気にしていたので近づいてみると、目の端に細かい毛が絡まっていました。
あわててぬるま湯で湿らせたガーゼで優しく拭き取り、事なきを得ました。もし放置していたら、毛による刺激で結膜炎になっていたかもしれません。
この経験から、私は換毛期には
を徹底しています。こうした工夫で、目のトラブルがぐっと減りました。

5.ウサギが結膜炎に!実際にあったトラブル体験
ある朝、「らむね」の左目の下が濡れているのに気づきました。最初は軽く考えていましたが、翌日には目やにが出始めたため、すぐに動物病院へ。診断結果は軽度の結膜炎。原因は、換毛期に飛んだ毛やホコリ、または細菌感染だろうとのことでした。
どんなに気をつけていても、予想外のトラブルは起きるものです。治療は1日3回の点眼。ですが、目薬嫌いな「らむね」は大暴れ。最初は押さえるだけで一苦労でした。そこで編み出したのが「目薬の後に大好きなりんごを一口」作戦。
これで少しずつ受け入れてくれるようになり、1週間ほどで無事完治しました。まんまるで輝く目が戻ったとき、涙が出るほどうれしかったのを覚えています。
6.ウサギの目の健康を守るためにできる5つのこと
ウサギの目はとてもデリケート。
小さな異変にもすぐ気づけるよう、日常からケアを心がけたいですね。
涙、目やに、ショボショボしていないか確認。
顔まわりを中心にこまめに毛を取り除く。
ホコリや抜け毛をためない環境作り。
空気清浄機や加湿器を活用して空気をきれいに保つ。
大きな音や急な光を避け、安心できる空間を作る。

まとめ:ウサギの目の特徴を知れば、もっと寄り添える
ウサギの目には、サバイバルの知恵と繊細な感受性が詰まっています。360度の視界、動くものに鋭い反応、繊細な健康サイン──。私自身、日々の暮らしの中で「らむね」や「ちょこ」の小さな仕草や目の輝きから、多くの事を学びました。
特に、目の健康はウサギの安心や信頼に直結していると実感しています。これからも、毎日の観察とケアを通じて、ウサギたちが安心して過ごせる環境を一緒に作っていきたいです。
読者の皆さんも、ぜひ愛兎の「目」に注目し、小さな変化を見逃さずに寄り添ってあげてください。
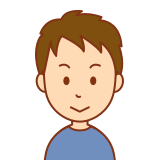
耳についてのお話は、こちらです。
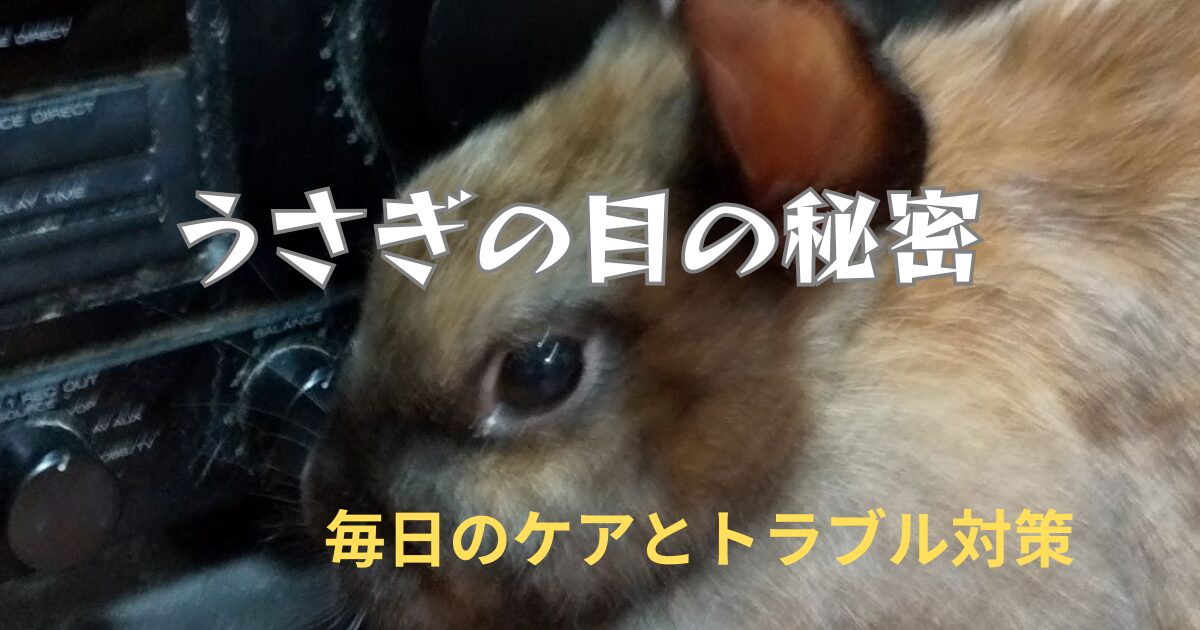


コメント