「きなこ」を迎えてから、ウサギの歯の健康について身をもって学ぶことになりました。最初は可愛さばかりに目がいっていましたが、ある日突然の食欲不振をきっかけに、歯のトラブルが命に直結する現実を体験しました。
この記事では、実際に「きなこ」と過ごした中で直面した困難や、その都度どう乗り超えたかを具体的にお伝えします。
1.「きなこ」の食欲がない!?異変に気づいたある日の朝
「ウサギの歯は前歯だけじゃないんです」——そんな事実を、私は「きなこ」の体調不良をきっかけに初めて知りました。
ある朝、いつものようにペレットの袋を開けると、「きなこ」は普段なら飛びついてくるのに、じっとケージの隅で丸まったまま。心配になって好物の乾燥パパイヤを差し出してみても、鼻先で軽く匂いを嗅ぐだけで食べませんでした。
普段と違う様子に私は慌ててスマートフォンで「ウサギ 食べない 動かない」などと検索をし、胃腸うっ滞という言葉に行き当たりました。「これはただ事じゃない」と直感し、すぐに動物病院に連れていきました。
動物病院で獣医さんから
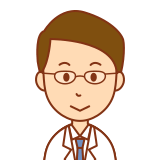
奥歯がわずかに尖って口の中を傷つけています。ウサギの歯は前歯だけでなく奥歯も一生伸び続けます。
と説明を受けました。
実際に診察台で「きなこ」の奥歯を専用の器具でチェックしてもらい、奥歯の一部が尖って口内を傷つけていることがわかりました。この時、初めて奥歯の異常が食欲不振の原因になることを実感しました。
言われてみれば、その頃の「きなこ」は柔らかいペレットや2番刈りの牧草ばかり食べていて、あまり固いものを噛む様子がなかったように思います。私自身、「ウサギ=前歯が伸びる」という程度の知識しかなく、奥歯にまで意識が向いていなかったのです。
先生の話では、ウサギの奥歯は見ることができないため、飼い主が異変に気づくのはかなり遅れがちだということでした。
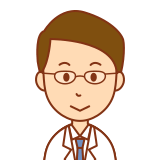
ウサギは歯の痛みを隠す動物です。異変に気づいた時には、すでに食べられなくなっていることも珍しくありません。
この言葉は、私の心に深く残りました。もしもあのとき、「ちょっと元気がないな」と感じる違和感を見過ごしていたら、もっと深刻な状態になっていたかもしれません。そう思うと、今でも背筋がゾッとします。
1-1.うさぎの「胃腸うっ滞(いちょううったい)」とは
①胃腸うっ滞の主な原因
牧草の摂取が少ないと、腸の動きが鈍くなります。
引っ越しや環境の変化、痛み、他の動物との接触などが原因に。
水分が不足すると、消化物が硬くなって移動しづらくなります。
歯が痛くて食べられない → 食べない → 腸が止まる という悪循環に。
身体を動かさないと、内臓の動きも鈍くなります。
②主な症状
- 食欲がなくなる(特にペレットや牧草を食べない)
- うんちの量が減る、もしくは出ない
- うんちが小さくなる、形が不揃い
- お腹が張っている、硬い
- 胃腸からゴロゴロと異音がする、または全く音がしない
- 元気がなく、じっとして動かない
1-2.自宅でできる予防法
- 常に新鮮な牧草(特にチモシー)を与える
- 毎日しっかりと水分補給させる(給水器より皿が飲みやすい子も)
- 適度に運動させるスペースを作る
- 歯の定期チェックをする
- 環境をなるべくストレスフリーに整える
2.ウサギの歯は一生伸び続ける!?基本構造と意外な事実
この体験をきっかけに、私は歯の構造や食生活について本気で見直すようになりました。そして今では、月に1度の定期健診や、噛む力を引き出す食材選びを欠かさず行うようになったのです。

2-1.ウサギの歯の構造ってどうなってるの?
ウサギの歯は全部で28本あり、前歯だけでなく奥歯(臼歯)も含まれます。以下は簡単な構造の説明です:
噛むことで自然に削られる:牧草(特に1番刈りチモシー)などの繊維質が豊富な食材が大切
2-2.よくあるウサギの歯のトラブル Q&A
Q:どうしてウサギの歯はトラブルになりやすいの?
A:ウサギの歯は「常生歯(じょうせいし)」といって一生伸び続けます。野生では草や木の皮を食べることで自然と削れますが、室内飼いでは柔らかい食べ物ばかりになると削りきれず、不正咬合(ふせいこうごう)=歯並びのズレや伸びすぎが起こることがあります。
Q:家でできる歯のケアは?
A:毎日の食事内容を見直すことが基本です。チモシーの1番刈りなど繊維質が多く、噛む回数の多い牧草を中心にすることが大切です。加えて、にんじんの葉や乾燥パパイヤなど「噛む」動作を促すおやつもおすすめです。
Q:どれくらいの頻度で動物病院に行けばいいの?
A:最低でも年に2〜3回の定期健診が望ましいですが、不安がある場合や何か様子が変だと感じたら、迷わず受診を。特に奥歯のチェックは素人では難しいため、月1回の健診を習慣にしている飼い主さんも多いです(我が家もそのひとりです)。
3. 歯が原因で命に関わることも…ウサギ特有の不正咬合とは
「きなこ」の一件以来、私はウサギの「不正咬合」という言葉を何度も調べました。
不正咬合とは、歯のかみ合わせが悪くなることで、歯が斜めに伸びたり、頬の内側や舌に当たって傷つけたりする症状。これが進行すると、ウサギは食事ができなくなり、胃腸が止まって命に関わることさえあります。
歯のトラブルを2度経験した我が家では、それ以降、「きなこ」の歯を守るために以下の工夫を徹底しています。
①「きなこ」が1番刈りチモシーをなかなか食べてくれず、何種類もの牧草を少量ずつ購入して”食べ比べ”を実施。最終的に香りが強めのブランドに落ち着き、今では1番刈りを主食にできるようになりました。
②常にかじれるものを用意しておくことも大切です。 我が家ではかじり木、藁ボールなどを定期的に交換して置いています。市販のかじり木だけでなく、知人からもらった無農薬のリンゴの枝を与えたところ、特に夢中でかじるようになり、歯の摩耗にも効果を感じています。
③月1回の動物病院通いは、最初は「ストレスになるのでは」と迷いましたが、奥歯の異常を早期発見できた経験から、今では必ず継続しています。診察後は必ずご褒美のおやつタイムを設け、「きなこ」も少しずつ通院に慣れてきました。
このように、日頃からの観察や食生活の工夫、そして定期的なプロのチェックを組み合わせることで、「きなこ」の健康を少しでも長く守っていけたらと思っています。
歯のトラブルは静かに進行することが多いからこそ、普段の「当たり前のような元気」をしっかり守ってあげることが、飼い主にできる一番のケアなのかもしれません。

5. ウサギを迎える前に知ってほしい“歯”の大切さ
ウサギの歯は一生伸び続けるため、自然に削れる環境を整えてあげることがとても重要です。放っておくと、伸びすぎて口の中を傷つけたり、食事がとれなくなったりすることも。食べられなくなると、栄養が足りず、腸の働きも悪くなり、命に関わる深刻な状態に陥る可能性があります。
「きなこ」との生活を通して、ウサギの歯の健康管理がどれだけ大切かを身を持って感じました。もしも少しでも「いつもと違う」と感じたら、迷わず行動することが大切です。これからウサギを迎える方、すでに一緒に暮らしている方も、ぜひご自身の経験や工夫を大切に、ウサギの健康を守ってあげてください。
6. まとめ:歯を制する者は、ウサギライフを制す!
今回は、ウサギの歯にまつわるさまざまなお話をお届けしました。
私自身、きなこの不調をきっかけに「ウサギの歯は一生伸び続ける」という大事な事実に気づかされました。正直、それまでは「牧草を食べてればOKでしょ?」くらいの認識しかありませんでした。
でも、歯がちょっと伸びすぎただけで、ごはんも食べられず、性格まで変わってしまうなんて……。ウサギにとって歯は、命に関わるほどの大事なパーツなんですね。
日頃の食事内容や、ちょっとした行動の変化を見逃さずにいることで、大きな病気を防ぐことができます。ウサギは話せないからこそ、「いつもと違う」を感じ取れるかどうかが飼い主の腕の見せどころ。
これからウサギを迎える方も、すでに一緒に暮らしている方も、ぜひこの機会に「うちの子の歯、大丈夫かな?」と見直してみてください。「歯を制する者は、ウサギライフを制す!」これ、あながち冗談じゃないかもしれませんよ。
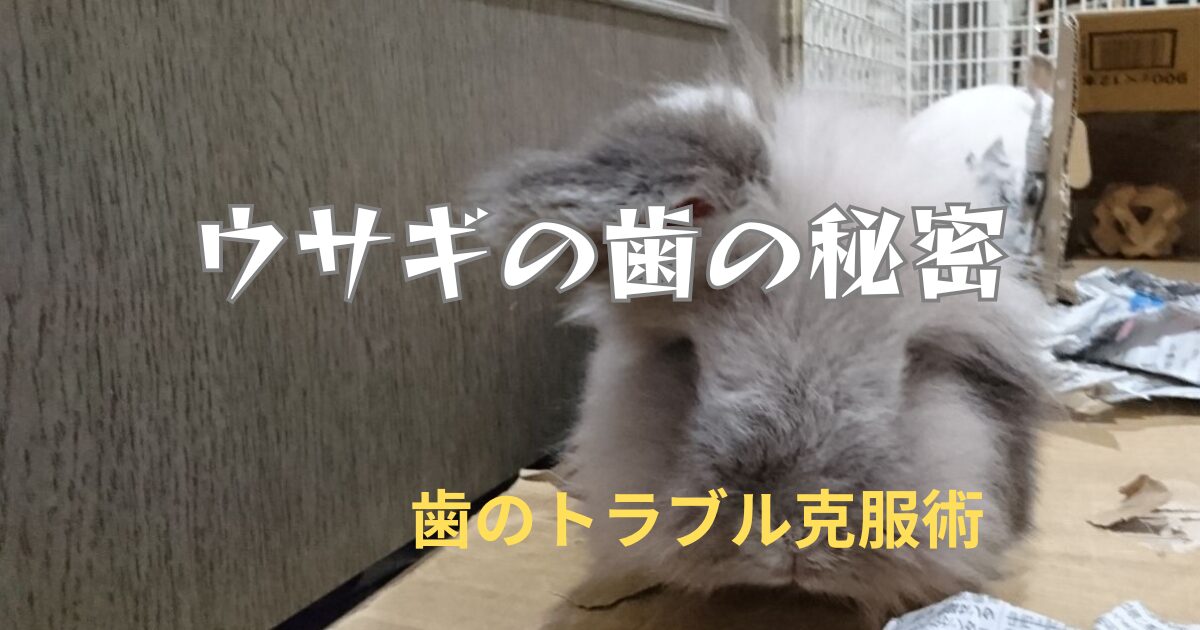



コメント