つぶらな瞳と愛らしい姿で私たちを魅了するウサギ。しかし、その繊細な心は、私たちが想像する以上に多くのことに不安や恐怖を感じています。何気ない日常の音や変化が、彼らにとっては大きなストレスとなることも少なくありません。
このブログでは、ミニウサギの「まろん」との暮らしを通して学んだ、ウサギが見せる様々なSOSのサイン、つまり警戒、不安、恐怖のサインを詳しく解説します。これらのサインをいち早く理解し、適切な対応をすることで、大切な家族であるウサギの心身の健康を守り、より穏やかで幸せな日々を送るためのお手伝いができれば幸いです。
1.知っておきたい!ウサギの警戒・不安・恐怖のサイン
好奇心旺盛で甘えん坊な我が家の「まろん」ですが、一方で、予期せぬ大きな音や初めて見るものには人一倍敏感です。そんな「まろん」との生活の中で、彼女が見せる様々な警戒・不安・恐怖のサインを学びました。
1-1.【音に敏感なサイン】アンテナのように立つ大きな耳
この行動は「敵から身を守る準備」の一環とも言えるでしょう。
【体験談】ある日の午後、窓際でくつろいでいた「まろん」が突然緊張した様子になりました。外から救急車のサイレンが響いてきた瞬間でした。彼女は耳をピンと立てて音源の方向へ向け、一切動かずじっと窓の外を見つめていました。
その姿はまるで「危険が迫っている」と訴えているかのようでした。この時、「まろん」がどれほど敏感なのか改めて感じました。
【飼い主ができること】ウサギが安心して暮らせる環境づくりには、大きな音への配慮が欠かせません。我が家ではテレビやオーディオ機器の音量を控えめに設定し、ドアや窓も静かに閉めるよう心掛けています。
また、掃除機など大きな音が出る家電を使う際には、「まろん」を別室へ移動させています。さらに最近ではケージ全体にタオルケットを掛けて防音効果を高める工夫も取り入れています。
1-2.【危険を察知】せわしなく動く小さな鼻
【体験談】ある日、新しい消臭剤(柑橘系)の香りがお部屋いっぱいに広がった時、「まろん」は普段通り遊び回っていた足取りが止まりました。そして鼻先だけ頻繁にヒクヒクさせながら消臭剤へ近づいて行ったのです。
その様子から明らかに警戒していることが分かったので、その場で消臭剤を片付けました。この経験以来、「まろん」の周辺環境には特別気遣うようになりました。
【飼い主ができること】強い香りの商品(芳香剤・殺虫剤など)はウサギエリアでは使用しない方が安全です。我が家では新しいアイテム導入時、「まろん」がどう反応するか観察する時間を設けています。
それでも警戒する場合には、そのアイテムは撤去しています。こうした小さな配慮こそ安心できる環境作りにつながります。
1-3.【身を守る本能】身を潜めて動かない防御姿勢
【体験談】 私が誤って近くで物を落として大きな音を立ててしまった際、それまで遊んでいた「まろん」はビクッとして動きを止め、体をペタンと床につけ、小さくなってしばらくの間、全く動きませんでした。
あたりを警戒して怖がっている様子を見ると、かわいそうなことをしたと思い、急に大きな音を立てないように注意しようと思いました。

【飼い主ができること】 ウサギがリラックスしている時に、急に大きな音を立てたり、予期せぬ動きで驚かせたりしないように注意しましょう。
1-4.【仲間への警告】後ろ足で地面を叩くスタンピング
【体験談】 我が家の「まろん」がスタンピングをするのは、主に私が彼女の嫌がる抱っこをしようとした時です。落ち着いていても嫌なものは嫌!という強い拒否の意思表示として、床を力強く何度も叩きつけます。
この行動を見た時は、抱っこしたいという気持ちを押さえ、そっとしておくようにしています。
【飼い主ができること】 スタンピングの原因を特定し、可能な限り取り除くように努めましょう。抱っこを嫌がるウサギには無理強いせず、他のコミュニケーション方法を試すことが大切です。また、暑かったり寒かったりしても、スタンピングします。
また、スタンピングが頻繁に見られる場合は、ストレスの原因がないか環境を見直しましょう。
1-5.【安全な場所へ】一目散に隠れる行動
【体験談】 激しい雷の音が鳴り響いた時、「まろん」は部屋の中を自由に探検している途中でしたが、一瞬止まった後、一目散に自分のケージの奥に隠れ、体を震わせていました。雷のような大きな音は、ウサギにとって非常に大きな恐怖です。
安心できるように、ケージの中にトンネルなど、隠れる場所を用意しようと思いました。

【飼い主ができること】 ケージの中に、ウサギが安心して隠れることができるトンネルやハウス、段ボールなどを設置してあげましょう。普段から隠れられる場所があることで、ウサギはより安心して過ごすことができます。
1-6.【緊張のサイン】速く浅い呼吸
【体験談】 健康診断のために動物病院へ連れて行った際、普段は落ち着いている「まろん」ががそわそわして、明らかに呼吸が速くなっていました。慣れない場所に緊張しているサインだと感じ、優しく声をかけながら体を撫でていると徐々に落ち着いてきました。
【飼い主ができること】 ウサギが緊張している様子が見られたら、無理に触ったりせず、静かに見守り、安心できるような声かけを心がけましょう。
1-7.【周囲を警戒】大きく開かれた瞳

【体験談】エアコンを掃除してもらうために、業者さんが来られた時、それまでうとうとしていた「まろん」はケージの中から目を大きく見開き、ピタッと止まったまま、不安げな表情で、その人の動きをじっと観察していました。その小さな体全体から、不安さがひしひしと伝わってきました
【飼い主ができること】 ウサギが警戒している人物や物に無理に近づけようとせず、ウサギが安心できる距離を保つようにしましょう。
1-8.【ストレス反応】食欲不振や排泄の変化
【体験談】 引っ越し後、新しい環境に数日間「まろん」はあまり動かず、ほとんどご飯を食べなくて、排泄物の量も明らかに減ってしまいました。環境の変化が彼女にとって大きなストレスになったと感じ、お気に入りの牧草やおもちゃを配置するなど、できる限りリラックスできる環境を整えるように努めました。
【飼い主ができること】 食欲不振や排泄の変化は、病気の可能性も示唆しています。数日続く場合は、自己判断せずに必ずウサギに詳しい獣医師に相談しましょう。日頃からウサギの食事量や排泄物の状態を把握しておくことが大切です。
1-9.【最終手段】身を守るための攻撃行動
【体験談】 うっかり「まろん」を強く抱きしめてしまった時、始めは抜け出そうとバタバタしていましたが、彼女は必死に私の手をかんで抵抗しました。これは、彼女が強い恐怖を感じていたサインであり、私の不注意を深く反省しました。
【飼い主ができること】 ウサギが嫌がることを無理強いせず、信頼関係を築くことを第一に考えましょう。攻撃的な行動が見られた場合は、ウサギが何に対して恐怖を感じているのかを理解し、その原因を取り除くように努めてください。
2.ウサギが安心して暮らすために~飼い主ができること~
ウサギが警戒、不安、恐怖を感じる原因を理解し、可能な限りそれらを取り除くことが、安心して暮らせる環境を作る上で最も重要です。
3.まとめ:ウサギのサインを理解し、より深い絆を
ウサギの警戒、不安、恐怖のサインを理解することは、彼らが安心して生活できる環境を整えるための第一歩です。これらのサインを見逃さず、ウサギの気持ちに寄り添った接し方を心がけることが、より豊かな共同生活を送るために不可欠です。日々の愛情深い観察を通して、あなたのウサギとの信頼関係を育んでいきましょう。
本記事は筆者の経験に基づいたものであり、全てのウサギに当てはまるわけではありません。ウサギの行動には個体差があります。もし、ウサギの行動についてご心配なことや、いつもと違う様子が見られた場合は、自己判断せずに、早めにウサギに詳しい獣医師にご相談ください。
獣医師の診断と指示に従うことが、大切なウサギの健康を守る上で最も重要です。
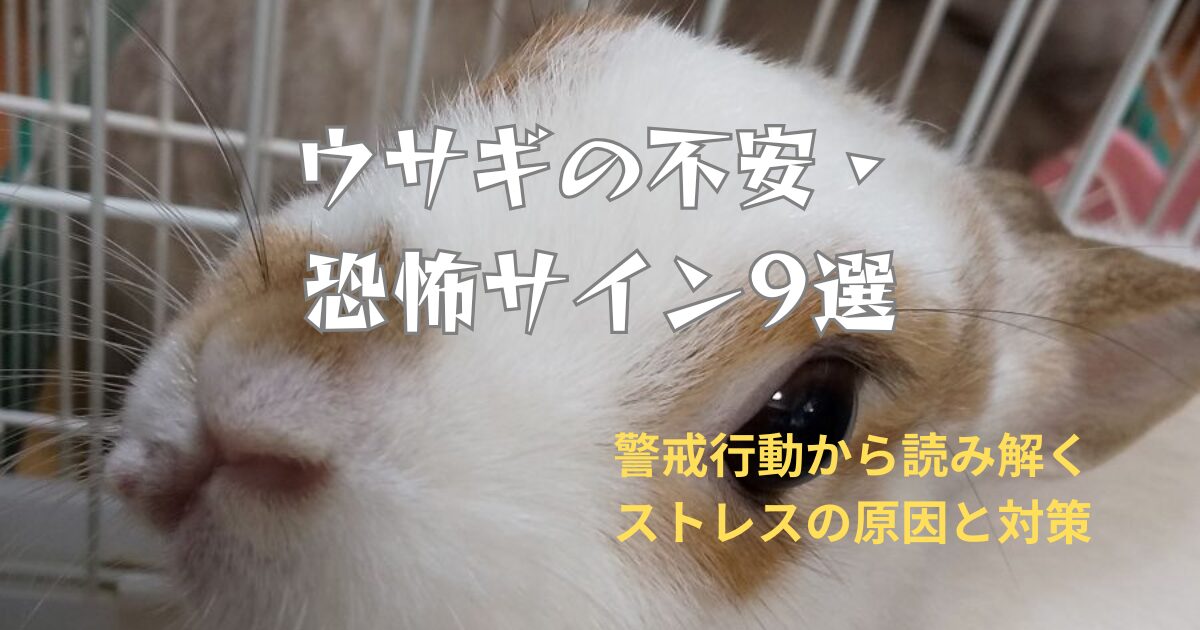


コメント