ウサギと暮らし始めた当初、私はその「ふわふわの耳」にすっかり魅了されました。ちょこんとついた大きな耳がぴくぴく動くたびに、「今どんな気持ちなのかな?」と話しかけたくなるほど可愛くて、まるで生きているぬいぐるみのようだと感じていました。
でも、ウサギとの生活が少しずつ長くなるにつれて、単なる“可愛いパーツ”ではないことがわかってきたのです。
今回は、我が家の愛兎「みるく」、そして後からやってきたロップイヤーの「ちび」との暮らしの中で気づいた、ウサギの耳の驚きの役割や健康管理のポイントについて、体験談を交えて詳しくご紹介します。
1. ウサギの耳は高性能レーダー!?
「みるく」との生活が始まったばかりのある夜、私はキッチンでそっとビニール袋を開けていました。すると、リビングの隅でくつろいていたはずの「みるく」が、ピンと耳を立ててこちらを凝視。次の瞬間、まるで合図を待っていたかのように走り寄ってきたのです。
この出来事が一度きりではなく、袋の音や冷蔵庫の開閉音など、私が何か食べ物を扱う度に毎回同じ反応を見せるようになりました。最初は「偶然かな?」と思っていましたが、「みるく」の耳の動きや表情を観察するうちに、「この子は私の行動パターンを耳で覚えているのかも」と気づきました。
ネットで調べると、ウサギの聴力は人間よりはるかに優れているとのこと。実際に、私が家族と小声で話している時も、「みるく」の耳がピクピクと動いているのを何度も目撃しました。
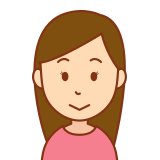
また、耳が左右で独立して動き、音の方向を即座に判断する姿を見て、「自然界で生き残るためにこんな進化を遂げたんだなぁ」と感動しました。
こうした日々の「気づき」がウサギの耳が単なる可愛いパーツではなく、生活の中で大切な役割を果たしていることを実感させてくれました。

2. 暑さ対策は耳がカギ!みるくとの初めての夏
「みるく」を迎えて初めての夏。7月のある朝、ふと耳を触ると、まるでお湯に浸したかのように熱くなっていて驚きました。急いで温度計を見ると、部屋の温度は28℃。エアコンはつけていたものの、窓際のケージは直射日光が当たりやすかったのです。
不安になって動物病院へ連れて行くと、
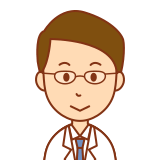
ウサギは耳で体温を調節するので、暑い日は耳が熱くなりますよ
それ以来、私は毎日2回、「みるく」の耳の温度をチェックするようになりました。エアコンの設定温度やケージの位置、保冷グッズの使い方も試行錯誤し、「みるく」の快適さを最優先に考えるようになったのです。
特に印象的だったのは、8月のある日、突然の停電でエアコンが止まった時。「みるく」の耳がどんどん熱くなっていくのを感じ、慌てて冷凍庫の保冷剤やペットボトルを総動員。冷たいタオルを耳の近くに置き、何とか無事に乗り切ることができました。
この経験から、夏場のウサギの健康管理は「耳の温度チェック」が命綱だと痛感しました。
♦ウサギの耳の体温チェック方法♦
- ウサギの耳の付け根付近をやさしく指先で触れます。
- 血管の様子がわかりやすく、体温チェックが簡単にできます。

3. ロップイヤーの「ちび」登場!耳の形と性格の関係とは?
「みるく」と暮らし始めて1年ほど経った頃、我が家に新しい家族「ちび」がやってきました。垂れ耳が特徴のロップイヤーです。最初の印象は、「みるく」とは正反対。「みるく」は新しい環境でもすぐに跳ね回るのに、「ちび」はケージの隅でじっとして動きませんでした。
数日観察していると、「みるく」は物音や人の動きにすぐ反応して耳を立てるのに対し、「ちび」はほとんど耳を動かさず、のんびりした様子。例えば、掃除機の音やインターホンが鳴っても、「みるく」は「何事!?」とばかりに耳をピンと立てるのに、「ちび」は全く動じません。
この違いが気になって調べてみると、
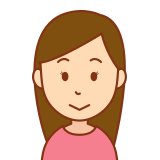
立ち耳のウサギは警戒心が強く、垂れ耳のロップイヤーはおっとりしている傾向があります。
実際に2羽を比べてみて、「性格や反応の違いは耳の形だけじゃなく、個性も大きいんだな」と実感しましした、

4. 冬も油断できない!耳で感じたみるくの異変
冬のある朝、「みるく」がケージの隅で丸くなり、いつもより元気がありませんでした。抱き上げてみると、耳がまるで氷のように冷たくなっていて、思わず「大丈夫!?」と声を上げていました。すぐに部屋の暖房を強め、「みるく」をブランケットで包んで温めると、30分ほどで普段通りに戻ってくれました。
この出来事以来、冬場は特に「耳の冷たさ」に注意するようになりました。毎朝毎晩の耳チェックと、ケージに小型ヒーターを設置するなど、寒さ対策を徹底しています。「みるく」の耳の温度を通じて、体調の「変化をいち早く察知できるようになったのは大きな収穫でした。
5. 耳の健康チェックが命を守る!私の習慣
耳は感情や体温だけでなく、病気のサインを見逃さない大事なパーツでもあります。「みるく」と暮らす中で、耳の健康チェックは私の習慣になりました。
| 我が家のルーティン | |
| ① | 毎週の耳の観察(赤み・傷・かゆがり行動のチェック) |
| ② | 月1回の動物病院での健康診断(耳掃除やダニチェックも) |
| ③ | 乾燥が気になる季節は加湿器で室内湿度を50%以上をキープ |
一度、「みるく」がしきりに耳をかくようになり、慌てて病院へ連れて行ったことがあります。診断は「乾燥による軽いかゆみ」。早めに気づいたおかげで大事には至りませんでした。獣医さんからは
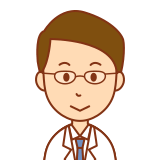
耳掃除は自己判断でやらず、必ず獣医師に相談してください
とアドバイスを受け、それ以来、月1回の健康診断も欠かさず受けています。
6. ウサギとの絆を深める“耳コミュニケーション”
毎晩、「みるく」の耳をなでながら「今日はどうだった?」と話しかけるのが、私のささやかな楽しみです。「みるく」の耳は、機嫌がよい時はふんわりと温かく、緊張しているときはピンと立っていることが多いです。
この「耳コミュニケーション」を通じて、言葉が通じなくてもお互いの気持ちを感じ合えるようになった気がします。

7.耳から始める健康管理のすすめ
ウサギの耳は、見た目の愛らしさだけでなく、実は健康管理や気持ちの変化を読み取るための大切なサインでもあります。私が「みるく」や「ちび」と一緒に暮らす中で一番驚いたのは、耳の温度や動き、しぐさひとつで「いつもと違うな」「今日はご機嫌かな」といったことに気づけるようになったことです。
特に体調の変化は、言葉を話せないウサギにとって耳が発信源のひとつになっていると実感しました。
たとえば、暑い日には熱を逃がそうとして耳がぽかぽかになりますし、寒い朝には耳が冷たくなっていることもあります。少し触っただけでその子の健康状態が伝わってくるような、そんな「耳のコミュニケーション」が、日々の生活に安心感をもたらしてくれました。
8.まとめ:ウサギを迎える方、すでに一緒に暮らしている方へ
ウサギの耳には感情や体調、健康状態など、たくさんのヒントが隠れています。私自身、「みるく」の耳を通じて小さな変化に気づき、早めに対応したことで大きなトラブルを防げた経験が何度もあります。ぜひ、毎日の「耳チェック」を習慣にして、大切な家族の健康を守ってあげてください。
この記事を通じて、読んでくださった方がウサギの耳にもっと注目し、大切な家族との絆を深めていけたら、こんなにうれしいことはありません。
※なお、ウサギの性格や反応は耳の形だけで決まるものではなく、それぞれの個体によって異なります。その子に合った接し方を見つけていくことも、飼い主としての楽しみのひとつです。
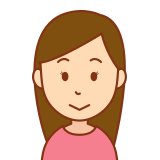
目のお話はこちらから。



コメント