愛らしいウサギとの暮らしは、心温まります。言葉を持たない彼らですが、実は豊かな「しぐさ」を通して、私たちに様々なメッセージを送っているのです。このしぐさを理解することは、ウサギとのコミュニケーションをより深くするために不可欠です。
本記事では、「きなこ」との日常で体験したエピソードを交えながら、ウサギが私たちに伝えようとしている可愛い「お願い」のサインを、詳しく解説します。
1.知っておきたい!ウサギの要求・興味・好奇心のサイン
1-1.【おねだりサイン】ケージをガジガジ・ガタガタ
【体験談】我が家の「きなこ」は、朝ごはんの準備中になると決まってケージの端で「まだなの?」とばかりに柵をカリカリし始めます。ある日、準備に少し手間取った際には、普段おっとりしている「きなこ」がケージを激しく揺らし、「早くして!」と全力でアピール。その真剣な表情に思わず笑ってしまいました。
【飼い主ができること】ウサギの気持ちを理解するためには観察が重要です。例えば、「きなこ」がケージをかじる時には、食事時間や遊び不足など原因を考え、安全なおもちゃやかじり木(リンゴやパパイヤの木など)を提供してみました。これによりストレス軽減につながりました。

1-2.【遊びのお誘い】足元をウロウロ・鼻でツンツン
【体験談】リビングで作業している時、「きなこ」は必ず足元まで来て鼻先で軽くツンツン。「あそぼうよ」と言わんばかりの瞳に負けてしまい、ついつい作業を中断してしまいます。また、一度ソファで休憩しているときには、私の手にそっと鼻先を押し付けてきて、その控えめながらも一生懸命な姿勢に心が癒されました。

【飼い主ができること】ウサギが遊びたい時には、安全なおもちゃ(柔らかいボールなど)を使って一緒に楽しむことで信頼関係が深まります。例えば、「きなこ」とボール遊びをした際には、その嬉しそうな表情を見るだけで疲れも吹き飛びました。
1-3.【好奇心旺盛】気になるものに鼻を近づけたり、持ち上げたり
ウサギは、生まれながらの探検家であり、非常に旺盛な好奇心を持っています。新しいおもちゃ、見慣れない家具、あるいは落ちている小さなゴミに至るまで、あらゆるものに対して強い興味を示します。
この行動は、ウサギの知的好奇心を満たし、日々の生活に刺激を与える上で非常に重要な役割を果たしています。
【体験談】 新しいトンネルを「きなこ」の遊び場に設置した時のことです。最初は、見慣れない大きな物体に「なんだろう?」と少し警戒した様子の「きなこ」でしたが、すぐに興味が勝ったようで、ソロソロと近づき、鼻をチョンチョンと近づけて匂いを嗅ぎ始めました。
そして、意を決したようにトンネルの中に恐る恐る入っていくのですが、まだ少し不安なのか、すぐに顔だけ出して、キョロキョロと周りの様子を伺っていました。でも、しばらくすると、トンネルの中が安全だと分かったみたいです。
今度はスルスルと奥まで進んでいき、反対側から顔を出して、まるで「どうだ、入れたぞ!」とでも言いたげな、得意げな表情で見つめてきたのが、本当に可愛くていい思い出です。
【飼い主ができること】 ウサギが新しいものに興味を示している時は、まずそれがウサギにとって安全なものであることを確認した上で、無理に遠ざけたり、驚かせたりしないようにしましょう。
自由に探索させることは、ウサギのストレス軽減や精神的な健康維持に繋がります。興味を示した後、すぐに遊び始めることもあれば、しばらく観察してから行動することもあります。
ウサギのペースを尊重し、新しい環境や物にゆっくりと慣れさせてあげましょう。ただし、誤飲の危険がある小さなものや、有害な可能性があるものは、ウサギの届かない場所に保管するように注意が必要です。

1-4.【アピール行動】前足をかける
これは、ウサギが自分の欲求や興味を飼い主さんに伝えようと、一生懸命コミュニケーションを取ろうとしているサインと言えます。
【体験談】 我が家の「きなこ」は、私がケージの掃除を始めようと扉を開けると、まるで「私もお手伝いする!」と言わんばかりの勢いで、すぐに前足をかけて「私も出る!私も出る!」と、全身でアピールしてきます。
その必死な様子に、「そんなに掃除が気になるの?それともただ遊びたいだけ?」と、思わず笑ってしまいます。また、ソファの上に置いてあるおやつに気づいた時や、私が手に持っているおもちゃに気づいた時も、後ろ足で立ち上がり、前足を必死に伸ばしてアピールしてくることがあります。
「あっちに行きたい!」「それ、欲しい!」という気持ちが、その小さな体から溢れ出ているようで、本当に愛らしい瞬間です。ただ、ソファの端に前足をかけて、体を乗り出そうとする時は、ハラハラドキドキ。
「そこは危ないからね!」と声をかけると、一瞬しょんぼりとした顔をするのですが、数秒後にはまた同じことを繰り返そうとするので、油断できません。その諦めきれない様子も、また可愛らしいのですが…。
【飼い主ができること】 ウサギが前足をかけてアピールしている時は、まずその理由を注意深く観察しましょう。「出してほしい」というサインであれば、安全な環境で適度な時間遊ばせてあげることが大切です。
「高い場所に興味がある」場合は、落下の危険がないか十分に確認し、安全な範囲で探索させてあげることもできます。ただし、危険な場所へ行こうとする場合は、優しく制止し、安全な遊び場に誘導しましょう。
ケージの扉を開ける際など、ウサギが予期せず飛び出してしまう可能性がある場合は、十分注意が必要です。また、「もっと構ってほしい」というアピールであれば、優しく撫でてあげたり、声をかけてあげたりするだけでも、ウサギは安心するでしょう。
1-5. 【遊びの催促】おもちゃをポイッ!くわえてアピール
これは、ウサギが飼い主さんとのコミュニケーションを心から求めており、一緒に楽しい時間を共有したいという、純粋な気持ちの表れです。
【体験談】 「きなこ」は、小さめの木のボールが大好きで、退屈するとよくそれをくわえて私の足元までトコトコと運んできて、私の目の前でわざとポイッと投げて、そして、まるで「さあ、どうだ!」と言わんばかりのキラキラした瞳で見上げてくるんです。
「これで遊んで!」というメッセージが、その一連の行動と表情から、ビンビン伝わってきて、もう無視することはできません!また、私がソファに座っていると、「きなこ」がお気に入りのボールを私の膝の上に、そっと置いて、そして、じっと私の顔を見つめてくることもあります。
その時、「あ、これは絶対に『一緒に遊んで』って言ってる!」と確信し、ボールを軽く転がしてあげると、「きなこ」は目を輝かせて嬉しそうに追いかけ、また私の足元に持って帰ってくる…その繰り返しが、本当に幸せな時間です。
【飼い主ができること】 ウサギがおもちゃを持ってきて遊びに誘っている時は、ぜひ積極的に応じてあげましょう。「わあ、すごいね!」「ありがとう!」と声をかけながら褒めてあげましょう。
一緒におもちゃを追いかけたり、優しく撫でてあげたりすることで、ウサギは「自分の気持ちが伝わった!」と感じて、大きな満足感を得られます。遊びを通して、ウサギとの信頼関係はより一層深まり、絆も強くなります。

1-6.【探索本能】掘るしぐさ
カーペットや毛布、クッションなどを前足でカキカキと掘るような仕草は、ウサギが持つ、巣穴を掘るという本能的な行動の名残と考えられています。野生のウサギは、外敵から身を守るための安全な隠れ家として、地面に複雑な巣穴を掘って生活します。
【体験談】 我が家の「きなこ」は、お気に入りのフリース素材のブランケットの上で、よく熱心に前足でカキカキと掘るような仕草をします。その真剣な表情を見ていると、思わずクスッと笑ってしまいます。
また、床に敷いた段ボールを、それはもうすごい勢いでバリバリと掘り返すこともあります。以前飼っていた別のウサギは、カーペットを一生懸命掘っていて、気が付いたらカーペットの下の床の木が見えていた、なんていう驚きの体験もありました。
【飼い主ができること】 ウサギが掘る行動を見せる場合は、まず、それが許容できる場所かどうかを確認しましょう。もしカーペットや家具など、掘ってほしくない場所を掘っている場合は、短く低い声で「ダメ」と優しく制止しましょう。
代わりに、あらかじめ掘っても良い場所(古新聞やわらなどを入れた箱、掘りやすい素材のマットなど)を用意しておき、そこに誘導してあげましょう。思う存分掘らせてあげることで、ウサギのストレス軽減にも繋がり、満足した得意顔を見せてくれるはずです。
1-7.【アイコンタクト】じっと見つめる瞳
注意を引こうとしている、何かを要求している、体調が優れないことを伝えようとしている、あるいは単に飼い主さんの様子を観察しているなど、その時の状況によって、様々な意味合いが考えられます。
言葉を話せないウサギにとって、視線は非常に重要なコミュニケーションの手段なのです。
【体験談】 「きなこ」が、何の前触れもなく、じっと私の目を、本当に真剣な眼差しで見つめてくる時があります。その時、「もしかして何か訴えているのかな?具合でも悪いのかしら?」と、私は少しドキッとします。
そして、「どうしたの?大丈夫?」と優しく声をかけながら近づき、体をそっと撫でてみると、私の手をペロペロと舐めてくれることがあります。これは、きっと「心配してくれてありがとう。ただ、甘えたかっただけだよ」という、愛情表現だったのでしょう。
また、朝起きてケージに近づくと、「きなこ」がじっとこちらを見つめていることもあります。そんな時は、「おはよう!ご飯の準備をするね」と声をかけると、嬉しそうに鼻をピクピクさせるので、「お腹が空いていたんだな」とすぐに分かります。
ある晩、私が少し体調を崩してソファで横になっていた時、「きなこ」はいつもはあまり来ない私のすぐそばまでトコトコとやってきて、心配そうに、本当に心配そうに私の顔をじっと見つめていたんです。
その優しい眼差しに、言葉はなくても「大丈夫?」と聞かれているような気がして、胸が熱くなりました。
【飼い主ができること】 ウサギがじっと見つめてくるときは、まず落ち着いて、その時の状況を振り返ってみましょう。餌や水の残量はどうか、ケージは清潔か、室温は適切かなど、基本的な環境を確認してみます。
そして、「何かお願いがあるのかな?」「どこか具合が悪いのかな?」と、ウサギの気持ちを優しく推測してみましょう。声をかけてみたり、優しく撫でてみたり、抱っこしてみたり、その時の状況に合わせて、ウサギが何を求めているのか、根気強く探ってみることが大切です。
もし、普段と違う様子で、元気がなく、じっと見つめているような場合は、体調不良の可能性も考えられますので、早めに獣医師に相談するようにしてください。

2.ウサギのサインを見逃さないために
ウサギのサインを見逃さないためには、日頃からウサギの行動を注意深く観察し、その時の状況と合わせて記録することが大切です。どのような時に、どのような仕草を見せるのかを把握することで、より早くウサギの気持ちを理解できるようになります。
まるで、我が子の成長を記録するように、日々の小さな変化に気づいてあげることが、より深い信頼関係を築く上で重要です。また、ウサギの飼育に関する信頼できる書籍や専門家のウェブサイトなどの情報を参考に、知識を深めることも非常に役立ちます。
様々な情報を得ることで、ウサギの行動の意味合いをより深く理解できるようになるでしょう。もし、いつもと違う行動が見られたり、食欲がない、排泄の様子がおかしい、元気がないなど、体調が悪そうな様子がある場合は、自己判断せずに、早めにウサギに詳しい獣医師に相談しましょう。
3.まとめ:サインを理解して、もっとウサギとの絆を深めよう!
ウサギの要求、興味、好奇心のサインを愛情深く理解することは、彼らとの絆を深め、より幸せで豊かなウサギライフを送るための、何よりも大切な鍵です。今回ご紹介した「きなこ」のサインを参考に、あなたのウサギがどんなメッセージを送ってくれているのか、じっくり観察してみてください。
日々の愛情深いコミュニケーションを通して、あなたのウサギとの信頼関係をさらに深め、言葉を超えた、温かい心の繋がりを育んで、より幸せな共同生活を楽しんでください。
【免責事項】本記事は筆者の体験に基づいたものであり、全てのウサギに当てはまるわけではありません。ウサギの行動には個体差があります。ウサギの健康や行動についてご心配な場合は、必ず専門の獣医師にご相談ください。
獣医師の診断と指示に従うことが、大切なウサギの健康を守る上で最も重要です。
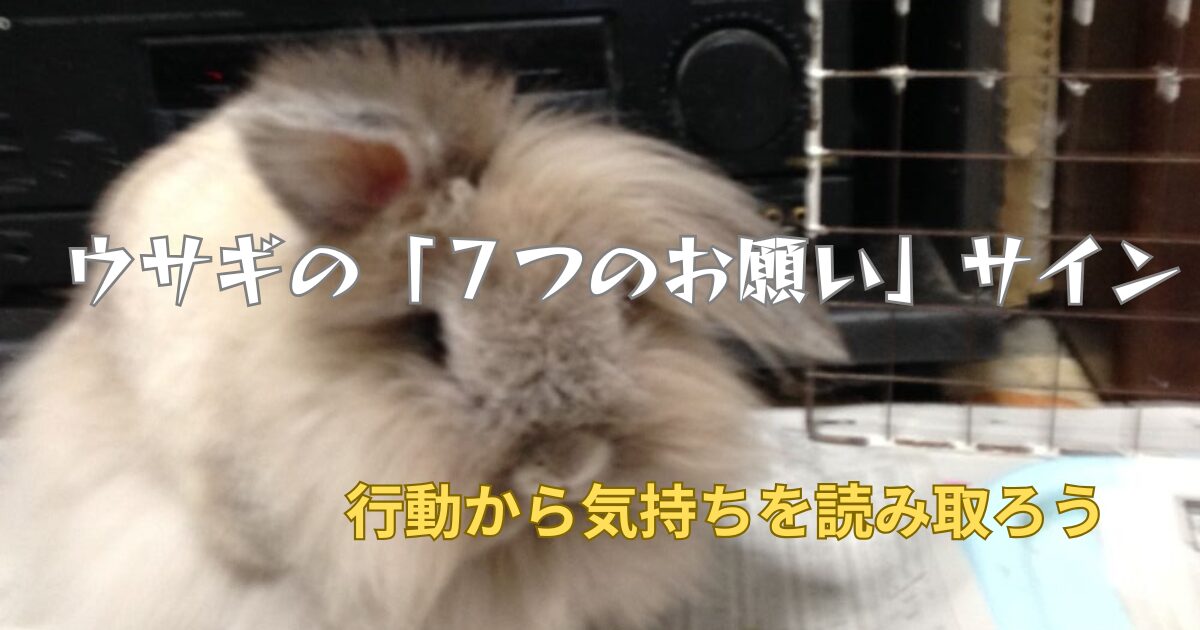


コメント