ウサギとの暮らしを始めた当初、私は「抱っこ=愛情表現」だと信じて疑いませんでした。しかし、うちにやってきた「まろん」は私の手が近づくだけで驚いて逃げてしまい、無理に抱き上げようとした結果、しばらく私を怖がるようになってしまいました。
そんな苦い経験から、どうすればウサギが安心して抱っこを受け入れてくれるのか、試行錯誤の日々がはじまりました。
この記事では、私の体験談をもとに、うさぎが安心できる正しい保定と抱っこの方法をお伝えします。
1.なぜうさぎは抱っこが苦手?
うちに「まろん」が来た日、私は嬉しさのあまり、抱っこして撫でようとしたのですが、驚いたように暴れて私の腕から飛び降りてしまいました。幸いケガはなかったものの、その日以来、私の手を怖がるようになりました。
2.信頼関係を壊さないための工夫
「抱っこは必要なときだけ」と自分にルールを課したのも、失敗から得た大きな学びです。健康チェックや通院など、どうしても必要な場面以外は、無理に抱き上げるのをやめました。その代わり、床に座っておやつをあげたり、そっと撫でる時間を増やし、「まろん」が自分から近づいてくれるまでじっくり待つことにしました。
実際、我が家のうさぎ「もこ」も、最初のころは抱っこされるのを極端に嫌がっていました。ある日、何の理由もなく可愛さから抱っこしようとしたところ、全力で逃げられ、その後しばらくは近づくだけで怯えた様子を見せるようになってしまいました。
それからは、必要なとき以外は抱っこを控え、床に座ってそばにいる時間を大切にするようにしました。すると少しずつ距離が縮まり、今では私の膝に自分から乗ってくることもあります。
そうしたときにだけ、そっと身体を支えるように抱きかかえ、「ありがとう」と声をかけるようにしています。
うさぎとの信頼関係は、時間と丁寧さの積み重ねだと感じています。抱っこは便利な手段であると同時に、ウサギにとっては強いストレスにもなりうる行為。だからこそ、「必要なときにだけ」というルールを守ることが、信頼を守る第一歩なのだと思います。

2-1.ウサギを膝の上に慣れさせるコツ【体験談】
我が家の「もこ」は、最初のころ膝の上にまったく乗ってくれませんでした。抱っこされるのが苦手な子なので、無理に乗せようとするとすぐに逃げてしまい、膝の上どころか近くに来ることさえ避けるようになってしまったのです。
「膝の上=安心できる場所」と思ってもらうために、私は「もこ」の大好きな乾燥パパイヤを使って誘導作戦を決行。さらに、「もこ」の匂いが付いたタオルを膝に敷き、警戒心を和らげました。
最初は前足だけちょこんと乗せるだけでしたが、数日かけて少しずつ距離を縮めました。撫でる時間を増やしたり、膝の上でしばらく過ごす練習もしました。今では自分から膝に乗ってくるように。焦らず、ウサギのペースに合わせることの大切さを実感しています。
2-2.撫でるときのポイント
抱き上げる時は、必ず後ろや横からゆっくり手を差し出し、まずは「今から触るよ」と声をかけて合図します。
私のうさぎ「もこ」も、最初は正面から手を出すとぴょんっと後ずさりして逃げていってしまいました。ですが、後ろからそっと手を差し出すと、匂いを確認しながらも落ち着いてその場にとどまってくれるようになりました。
①人差し指と中指でうさぎの前足の付け根をそっと支え、胸の部分を手のひらで包むようにします。このとき、強く握らず、ふんわりと体を支えるように意識するのがポイントです。
②もう片方の手でお尻をしっかりと支えながら持ち上げます。そのまま自分の体に密着させて安定させるようにしています。お尻の支えが甘いと暴れる原因になるので、ここは特に注意しています。
私が始めて「もこ」を抱き上げたとき、緊張してお尻の支えが甘くなってしまい、「もこ」がバタバタと暴れて、逃げたことがありました。うさぎにとってお尻が不安定な状態は非常に不安を感じるようで、その後もしばらくは抱っこを嫌がるようになってしまいました。
抱き上げる際は、必ず両手で体をしっかりと支えることが大切です。「もこ」は今では比較的落ち着いて、抱っこさせてくれるようになっています。抱っこは「信頼されている証」でもあるので、焦らず丁寧に、安心できる環境を整えてあげましょう。

3-2.応急処置・診察時の保定【体験談】
応急処置や診察など緊急時に短時間だけ行う保定方法です。うさぎをしっかり固定して動きを抑えることで、安全に処置ができます。
動物病院での診察時、どうしても暴れてしまう「らむね」には、獣医さん直伝の「首の後ろの皮膚を優しく包む」保定法が役立ちました。普段は使いませんが、診察台の上で一時的に動きを止めるにはとても有効でした。
ただしウサギにとってはストレスが大きいので、あくまで短時間・緊急時だけにしています。
①首の後ろの皮膚を親指と指全体でやさしく包むようにつかみます。引っ張るのではなく、軽く圧をかけて「包み込む」ような感覚です。このとき、「らむね」もピタッと動きを止めて、目を細めてじっとしてくれました。暴れるのをやめ、驚くほど落ち着いてくれたのです。
②もう片方の手でお尻をしっかりと支えながら、体を水平に保ってそっと持ち上げます。体を傾けすぎるとバランスを崩して怖がるので、なるべくまっすぐの姿勢を意識しました。私の腕の中で静かに診察を受けている「らむね」の姿を見たときは、本当にホッとしました。
うさぎにとって首の後ろをつかまれるのは、本能的に「捕まった」と感じる不安な体勢でもあるため、日常的な抱っこやスキンシップには向きません。
それでも、病院での診察時や緊急時にはとても有効な方法です。焦らず、うさぎの気持ちを考えながら、必要なときだけ短時間で使うことが信頼関係を壊さないコツだと思います。

3-3.タオル保定・バニーバリトリング【体験談】
爪切りや診察など、どうしても暴れてしまう時は「タオルで包む」方法が私の定番。バスタオルで体全体を優しく包み、顔だけ出してあげると、「らむね」も次第に落ち着いてくれます。
最初はバタついていましたが、包み方を安定させることで安心してくれるようになりました。作業後はすぐにタオルから出し、おやつで「がんばったね」と声をかけるのも忘れません。
タオルはバスタオルくらいのサイズを使うと余裕があり、しっかりと全身を包めます。顔だけを出すように包むことで呼吸もしやすく、視界も確保できるので、不安になることはありません。
この方法は特に爪切りや診察時に便利で、足が動かせない状態になることで、うさぎ自身も落ち着きやすくなります。最初はバタつくこともありますが、包み方を安定させると次第にリラックスしてくれるようになります。

私も「らむね」の爪切りをするときは、必ずこのタオル保定を使っています。処置中に暴れてケガをすることも防げるので、うさぎにとっても私にとっても安全です。
必ず床近くで行うようにしましょう。抱っこしたまま高い位置で作業すると、万が一暴れたときに落下の危険があります。うちはテーブルの上で行っていたこともありましたが、一度「らむね」が暴れた拍子にヒヤッとしたことがあり、それ以来、必ずクッションを敷いた床の上で作業するようになりました。
3-4.爪切り時の保定(2人作業が理想)
①準備物
- 小動物用爪切り
- タオル
- 懐中電灯(血管確認)
- ごほうび
②手順
爪切りは2人で行うのが理想ですが、私は一人の時はタオルでしっかり包み、片方の足だけをそっと取り出してカットしています。最初はどこまで切っていいかわからず、ほんの数ミリだけ切ることもありましたが、「安全第一」を心掛けています。
もし出血してしまったときは、すぐに止血剤とティッシュで対処。終わった後は必ずおやつでフォローして、嫌な思い出にならないようにしています。
4.まとめ:保定はうさぎとの信頼を深める時間
ウサギとの信頼関係は、一朝一夕では築けません。私自身、何度も失敗し、落ち込むこともありましたが、「まろん」と「もこ」と過ごす中で、少しずつお互いの距離が縮まっていくのを感じています。
保定や抱っこは、ウサギにとっても飼い主にとっても「信頼を深める時間」。焦らず、ウサギのペースを大切にしながら、これからも一緒に成長していきたいと思います。
みなさんのうさぎライフが、もっと穏やかで幸せなものになりますように。






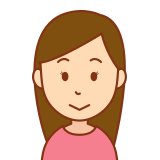


コメント