子ウサギを迎えることは、まさに小さな命とのかけがえのない出会いです。今回は、私自身のリアルな体験談をもとに、生まれたばかりの子ウサギが生後6ヵ月になるまでにどのように成長していくのかを、子ウサギの成長過程と気をつけるべきポイントを徹底解説します。
初めてウサギを飼う方にもわかりやすく、安心してお世話ができるよう、できる限り具体的に内容をまとめました。
- 1. 子ウサギの成長スケジュール
- 2.飼い主が気をつけるべき5つのポイント:体験から学ぶ
- 3.成長に合わせたケージと環境づくり :うちの子ウサギのケージレイアウト失敗談
- 4.愛情を注げば、ちゃんと伝わる:うちの子ウサギが人懐っこくなった理由
- 5.子ウサギの成長って、本当にあっという間
- 6. まとめ:子ウサギとの暮らしは毎日が学び
1. 子ウサギの成長スケジュール
1-1.生後0〜7日の子ウサギ:命のはじまりを見守って
初めて「こむぎ」が生まれた朝、ケージをそっと覗くと、母ウサギの足元で小さな体が震えていました。それが、生後0日の新生児ウサギたちとの最初の出会いでした。
①見た目・身体的特徴:小さな命の誕生
重さはわずか30〜50g。掌にそっと乗せると、じんわりと伝わる体温に「この命を守りたい」と強く思ったのを今でも覚えています。最初は毛もなく、呼吸も速くて不安でしたが、毎朝「今日も元気かな」とドキドキしながら巣を覗く日々でした。
②授乳と母ウサギとの関係:母の本能に委ねる
最初は、巣箱に母ウサギが入っている姿を見かけないので「育児放棄してるのでは?」と焦りました。インターネットで調べると母ウサギは敵に巣の場所を悟られないように、授乳のときだけそっと現れて、ほんの数分で去っていくそうです。
授乳しているかどうかを確認するため、私は朝と夜にそっと子ウサギたちのお腹を見ました。ふっくら丸く、ほんのりピンク色の艶があれば、ちゃんと母乳を飲めている証拠です。母ウサギの姿を見かけなくても、お腹が満ちている様子に何度も安心させられました。
③温度・環境管理:暖かさは命を守る盾
生後間もない子ウサギたちは、自分で体温調節ができません。そのため出産直後からエアコンを26℃に設定し、夜はケージの周りに毛布をかけて保温していました。冷え込んだ夜はペット用ヒーターも追加。
母ウサギが自分の毛をむしって巣を作る姿を見て「本能ってすごい」と感心したことも印象に残っています。もし巣材が少ない場合は、清潔な綿や柔らかいティッシュなどを補助的に使うと良いという情報も得ました。
④健康チェックポイント:日々の観察がカギ
この時期の子ウサギは、とにかく「観察」が重要です。私は毎朝そっと巣をのぞいて、子ウサギたちが動いているか、お腹が膨らんでいるかを確認していました。
元気な子は、目を閉じたままでも小さくうごめいていて、指先でそっと触れると反応がありました。逆に、動かずぐったりしている子がいたときは、心配で一日中そわそわしていました。
授乳がうまくいっていない子が一羽だけ明らかに小さく、弱っていたこともありました。獣医さんに相談し、猫用のミルクをシリンジで与える方法を教わり、慎重に人工授乳を開始しました。うっかりミルクが気道に入ってしまうと命に関わるため、とても緊張しながらの作業でした。
⑤注意点:新生児期の子ウサギは「命の奇跡」
生後0〜7日の子ウサギは、まさに命のはじまりの瞬間。見た目も行動も、まだ「ウサギらしさ」は感じられませんが、その小さな体からは確かな生命力が感じられます。
この時期のお世話は、「手を出しすぎないこと」「静かに見守ること」「環境を整えること」が基本です。私自身、たくさんの失敗と不安を経験しましたが、それ以上に、成長していく姿を見る喜びがありました。
⑥まとめ:生後0~7日
- 最初は無毛で、毎日少しずつ産毛が増えていくのが楽しみでした。
- 母ウサギがそばにいなくても、お腹がふっくらしていれば安心できると知りました。
- 夜間の冷え込みにはヒーターを追加し、26〜30℃になるように温度計でこまめにチェック。
- 動きが鈍い日やお腹の張りに気づいたときは、すぐに獣医さんに相談しました。
- 過干渉し過ぎて母ウサギが警戒したこともあり、そっと見守る大切さを学びました。
⑤まとめ:生後8~14日
- 生後10日~12日前後に目が開き始め、両目が開いたら巣の中を回り、外への興味が出てきました。
- 体中の毛が生えそろい、模様もはっきりして、個体の区別ができるようになり、名前を付けるのが楽しみになりました。
- 栄養はまだ母乳だけで、お腹がぽっこりしていたら、ちゃんと飲めていると安心しました。
- 室温26〜27℃に保ち、巣箱内にはヒーターを設置。巣箱の位置にも気を配りました。
- 触りたい気持ちを我慢して、母子のウサギのつながりを大切にしました。
1-3.生後15〜21日:ぴょんぴょん跳ねる小さな冒険者たち
我が家の子ウサギたちが生後15日を迎えた頃、ふわふわだった産毛はすっかり整い、目もぱっちり、耳もしっかり上がって、見た目も動きもぐんとウサギらしくなってきました。
①見た目の成長:ますますウサギらしさが出てくる
生後2週を過ぎると毛が密になり、つやも出てきました。我が家の子ウサギたちは親にそっくりな模様がはっきりしてきて、「お母さん似だね」「パパに似てるね」と家族で盛り上がっています。
目はしっかり開き、動くものをじっと見たり、音にも敏感に反応するようになりました。特に袋の音には「ごはんかな?」と反応する姿がたまりません。抱っこするたびに「重くなったな」と感じるようになり、体重は200〜300gに。ふっくらとした「ちびウサギ」に成長中です。
②行動の変化:好奇心でいっぱい
ある朝、1匹が巣箱の外にちょこんと座っていてビックリ!母ウサギのあとをついて歩くようになり、好奇心が一気に芽生えたようでした。その後、兄弟たちも続々と探検を始め、部屋をウロウロ。見ていて目が離せません。
足の力もついてきて、小さくジャンプする姿も。まだ不安定ですが、その様子がとても微笑ましく、転がってしまう姿に家族で笑ってしまいました。
巣の中では、兄弟でじゃれ合うようになり、耳をかじったり鼻をくっつけ合ったり。これが社会性の始まりかな、と感じます。
③食事:離乳の第一歩
生後3週目に入ると、母ウサギが食べているアルファルファの牧草に興味を持ち始めました。パクッと食べる姿がまるで真似っ子しているようで、とても可愛い瞬間でした。
ある日、兄弟の後ろにくっついていた子が、突然その糞をパクリ。「えっ!?」と焦りましたが、これも腸内環境を整える大事な行動だと知り安心しました。主な栄養源はまだ母乳。母ウサギにぴったりくっついて授乳する姿は壮観です。
④飼育環境のポイント:室温に注意
この頃から室温管理も少しずつ変えていきました。毛がしっかりしてきたので、部屋の温度は20〜25℃を意識して、過度な保温はせずに。とはいえ、急な寒暖差がないようにヒーターは夜間だけ入れて様子を見ました。
「そろそろ巣が狭そうだな」と思い、タイミングを見て少しずつ変更。急に環境が変わらないよう、母ウサギのにおいが残るように工夫しました。
⑤まとめ:生後15~21日
- 毛が生えそろい、体重も200〜300gに増加。見た目もウサギらしくなりました。
- 巣の外へ冒険するようになり、跳ねる練習やじゃれあいをしていました。そのため誤飲・事故防止の安全な行動スペースを確保しました。
- 母ウサギを見て、牧草やペレットに興味を持ちだしましたが、まだ母乳が必要です。食糞が始まり、正常に成長していると安心しました。
- 室温を20〜25℃に設定するように変更しました。巣箱の撤去タイミングの時期になり、徐々に変えていきました。
1-4.生後1ヵ月の子ウサギ:はじめての“ひとり立ち”準備期間
生後1ヵ月を迎えるころの子ウサギは、見た目も行動もぐんとウサギらしくなってきます。まさに“赤ちゃん”から“子ども”への移行期で、離乳が始まるとともに自立の準備も進みます。
①見た目の成長:ぬいぐるみみたいな可愛さに拍車!
うちの子ウサギ「こむぎ」は生後1ヵ月で約350g。抱っこすると手のひらにしっかり重みを感じ、毛並みもふわふわの艶やかな被毛に。
この頃から音や匂いへの反応が敏感になり、冷蔵庫の音や足音にも耳がピクッ。大きな音にはビクッと驚くこともあるので、テレビの音量は控えめにしています。
顔立ちも変わり、鼻が高くなり耳もピンと立ちました。観察する姿が頼もしく、つい写真を撮りたくなります。
②行動の特徴:元気いっぱい、遊び心も芽生えて
1ヵ月を過ぎると、「こむぎ」は筋肉がついてケージ内をぴょんぴょん跳ね回るように。トンネルに飛び込んだり段差に登ったりと活発です。排泄も決まった場所でするようになり、トイレ砂を置いたら意外とすぐ覚えてくれました。成功したときにしっかり褒めるのがポイントです。
また、手の動きや声にも興味を持ち、「おいで」に反応して鼻先でツンと触れる姿がとても愛らしく、スキンシップが楽しくなります。
③食事:離乳のスタート、母乳から少しずつ自立へ
この頃になると、「こむぎ」は一日の中で何度もアルファルファに口をつけていて、徐々に食事の中心が母乳から牧草に移っていくのが分かりました。ウサギ用のベビーペレットも、この時期から少しずつ与えるようにしました。成分表示をしっかりチェックして、年齢に合ったものを選ぶことが大切です。
「もう離乳かな?」と思っても、実はまだ母乳も大切。完全に断乳できるのはもう少し先。「こむぎ」も、牧草を食べながらも時々母乳を飲んでいる様子が見られました。
④健康チェックと注意点:体調管理が大切な時期
この時期のウサギは「盲腸糞」を食べて腸内環境を整えます。「こむぎ」も静かな時間にこっそり食べていて、健康の証です。便や尿のチェックも大切で、丸く乾いたコロコロ便が正常。ベタつきや異常な色には注意が必要です。
ストレスにも敏感な時期なので、私は掃除機を使うとき「こむぎ」を別の部屋で過ごさせていました。
⑤お世話のポイント:環境と接し方にひと工夫
動きが活発になってくるこの時期。「こむぎ」には、広めのケージと一緒に、小さなトンネルや巣箱も設置しました。走り回った後にトンネルで一息つく姿は本当に愛らしいものです。
抱っこができるようになったとはいえ、「こむぎ」にとってはまだ緊張の時間。長時間構いすぎるとストレスになるため、数分のふれあいを何度かに分けて、少しずつ距離を縮めていきました。
⑥まとめ:生後1ヵ月
- 見た目は毛艶が出て、体重300〜400g前後になり、ぬいぐるみみたいな可愛さになりました。
- ジャンプしたり、走り回ったり活発に動くようになりました。そろそろトイレの練習も可能になりました。
- アルファルファやベビーペレットを食べるようになり、母乳の量が減りました。そろそろ離乳の時期です。
- 毎日便や尿のチェックをして健康に気を付けました。
- 危なくない運動スペースを確保し、部屋んぽの時に、数分に分けて優しいスキンシップを試みました。
1-5.生後1ヵ月~1ヵ月半の子ウサギ:自立の時期
生後1ヵ月〜1ヵ月半の子ウサギは、ちょうど離乳が始まり、親ウサギから少しずつ自立していく時期にあたります。見た目はとても小さくて愛らしいですが、体の中では大きな変化が進んでいます。この時期の特徴を、わかりやすくまとめますね。
①見た目と体の変化
生後1ヵ月半の頃、うちの子ウサギは手のひらにすっぽり収まるほど小さく、体重は約400gでした。抱き上げるたびに重さの変化を感じ「本当に生きているんだ」と感動したのを覚えています。
この時期の毛は「子ども毛」と呼ばれ、非常に柔らかくてふわふわ。目と耳は完全に開いており、周囲の音や動きに敏感に反応します。初めて私の声に反応して耳をピクッと動かした瞬間は、今でも忘れられません。

②性格・行動:社会性の学び
生後1ヵ月半を迎える頃、「こむぎ」はぴょんぴょんと飛び跳ねるように。その成長の早さに毎日驚かされました。
好奇心旺盛だけど少し臆病で、冷蔵庫の音や突然の動きにびっくりして逃げることも。だから、接するときは静かに声をかけ、そっと手を差し出すように気をつけていました。
兄弟とのじゃれ合いから加減を学んでいる様子も見られ、「自然な成長環境の大切さ」を感じました。「こむぎ」との毎日は、発見と癒しの連続です。
③離乳のスタート:食事の変化
この頃になると、「こむぎ」は母乳を飲みつつ、アルファルファにも興味を示し始めました。最初は一口くわえて落とすだけでしたが、少しずつモグモグと食べるように。
獣医さんから「急な食事の変化や不衛生な環境は下痢の原因になる」と聞き、ペレットは慎重に増やし、ケージも清潔に保つようにしました。便や食欲を毎日チェックしながら、「この子の健康は私が守るんだ」と実感する日々でした。
④健康管理
うちの子ウサギは毎日何度も排泄していて、盲腸糞をちゃんと食べているかをチェックするのが習慣でした。獣医さんから、それが栄養吸収に大切だと聞いていたので特に気をつけていました。
ある日、いつもより元気がなく食欲も落ちていたので、体重を測ると少し減っていて心配に。すぐ病院へ連れて行ったところ、早めの対応が良かったようで大事には至りませんでした。
この経験を通して、日々の小さな変化に気づくことの大切さを実感しました。手間はかかりますが、だからこそ一層かわいく感じます。
⑤お世話:室温管理
この時期の子ウサギは、体温調節がまだうまくできないため、室温を20〜25℃に保つように心がけました。特に冬場は、ケージの近くに小さなヒーターを設置し、寒さ対策をしました。また、ケージ内には隠れられる小さなハウスを置き、安心できる空間を作りました。
床材にも注意が必要で、足が滑らないように柔らかいマットやタオルを敷きました。これにより、足への負担を軽減し、快適に過ごせるようにしました。
⑥まとめ:生後1ヵ月~1ヵ月半
- 体重は約400〜500gぐらいに増え、離乳食も始めました。
- 相変わらず好奇心旺盛で、何にでも興味をもちます。トイレの練習をこの頃に始めました。
- 毎日便のチェックをし、盲腸糞が残っていないかもチェックしました。ストレス管理をすると盲腸糞が残らないことに気づきました。
- 室温を20〜25℃に保つように心がけ、特に冬場は、ケージの近くに小さなヒーターを設置し、寒さ対策をしました。
1-6.生後1ヵ月半〜3ヵ月:“幼児期”の大切な日々
生後1ヵ月半〜3ヵ月の子ウサギは、「赤ちゃんウサギ」から「子どもウサギ」へ、そして「若ウサギ」へと変わるような時期です。
①体の発達と外見の変化:まるでミニサイズの変身ショー
「こむぎ」は毎週100gずつ成長し、3ヵ月になる頃には800g近くに。手に乗せたときのずっしり感に「大きくなったなぁ」と感動しました。生後2ヵ月頃には、立ち耳がピンと立ち、音に反応して動く姿がかわいくて写真をたくさん撮ったのを覚えています。
顔つきも丸顔からキリッとした印象に変わり、毛並みも柔らかさの中にコシが出てきた感じがして、成長を感じる毎日でした。

②行動の特徴と変化:毎日が新しい発見
「こむぎ」が部屋んぽを始めたころは少しおっかなびっくり。でも数日後には、ジャンプや急停止からの“ジャンプターン”を披露!初めて見たときは「これがウサギダンスか!」と感動しました。
ただ、コードや家具をカジカジし始めたので、慌ててかじり木やおもちゃを設置。今思えば、それも成長のひとつだったのかもしれません。
名前を呼び続けていたら、こちらを見たり鼻でツンツンしてきたり。小さな信頼の積み重ねに、心が温かくなりました。
③食事のポイント:体の中から健康に
当初はアルファルファ中心の食事でしたが、2ヵ月過ぎから少しずつチモシーに切り替え始めました。最初は見向きもしなかったチモシーも、混ぜながら与えることで少しずつ食べてくれるように。子ウサギたちの牧草をチモシーを主食に切り替える準備期間です。
ペレットは1日2〜3回、時間を決めて与えるようにしました。朝ごはんの時間になると、ケージの中で「待ってたよ〜!」というようにぴょんぴょん跳ねてアピールする姿がとってもかわいかったです。
④健康管理と注意点:大切な命を守るために
「こむぎ」が生後3ヵ月になるころ、初めての換毛期がやってきました。ふわふわの毛が抜けて部屋中に舞い、思わず掃除が日課に。最初は手で軽く撫でながら毛を取っていたのですが、おやつを使って少しずつブラシに慣らしていきました。
換毛期は毛球症が心配だったので、牧草を多めに用意し、部屋んぽも長めに。元気に過ごしてくれると、こちらも安心します。
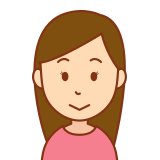
換毛期や毛球症が心配な方はこちらへ。
また、生後2ヵ月半ごろには動物病院でワクチン接種の相談も。地域の感染症リスクを聞けたことで、備えの大切さを実感しました。
⑤お世話としつけ:少しずつ、大人の階段を上る子ウサギ
最初はトイレの失敗も多かった「こむぎ」ですが、生後2ヵ月を過ぎるころにはケージ内でしっかりできるように。成功したときは「えらいね!」と声をかけるのが習慣になりました。
部屋んぽも最初は10分ほどでしたが、徐々に30分に延長。配線を隠したり危ない場所を塞いだりと、安全対策に力を入れました。夜は膝の上でなでながら過ごすのが日課。無理に抱っこせず、安心できる時間を毎日少しずつ積み重ねています。
2.飼い主が気をつけるべき5つのポイント:体験から学ぶ
子ウサギとの生活は、日々の小さな気づきと工夫の積み重ねです。私自身の体験をもとに、飼い主が気をつけるべき5つのポイントをご紹介します。
① 温度管理は最重要
子ウサギは体温調節が苦手で、室温の変化に敏感です。我が家では、生まれて1週間は室温を26~30℃、毛が生えてくる2週間目ぐらいまでは26~27℃、毛が生えそろうそれ以降は24~25℃に室温を設定しました。冬はヒーターも使用しています。
特に夏場は、エアコンの設定温度を24〜24.5℃にしても、うさぎが暑そうにしていることがありました。そのため、うさぎが自分で快適な場所を選べるよう、部屋の隅にひんやりしたフローリングスペースを用意しています。
② 食事管理:牧草と水を常に用意
子ウサギの主食はチモシー(牧草)と新鮮な水です。生後1ヶ月を過ぎると、アルファルファが原料のペレットを少しずつ与えました。我が家では、給水ボトルと器の両方を用意し、ウサギが飲みやすい方法を選べるようにしています。また、水は毎日交換し、清潔を保つようにしています。
③ ケージと遊び場の清潔さを保つ
糞や尿をこまめに掃除し、ケージ内を常に清潔に保つことが大切です。我が家では、毎日トイレの掃除を行い、週に一度はケージ全体を清掃しています。また、ウサギのお気に入りのぬいぐるみが汚れてきた際には、洗濯して清潔を保つようにしています。
④ 抱っこの練習はゆっくりと
子ウサギは抱っこが苦手なことが多いため、無理に抱こうとせず、まずは撫でることから始め、信頼関係を築いてから徐々に慣らしましょう。我が家のうさぎも、最初は抱っこを嫌がっていましたが、毎日少しずつ撫でる時間を増やし、安心感を与えることで、徐々に抱っこにも慣れてきました。
⑤ 異変にすぐ気づく観察力
「いつもと違う行動」や「食欲の変化」など、小さなサインを見逃さないことが命を守るカギです。我が家では、毎日うさぎの様子を観察し、毛並みや目の輝き、排泄物の状態などをチェックしています。異変に気づいた際には、すぐに獣医さんに相談するようにしています。
3.成長に合わせたケージと環境づくり :うちの子ウサギのケージレイアウト失敗談
最初は60cmのケージで十分だと思っていましたが、3ヵ月を過ぎて「こむぎ」がジャンプやダッシュを始めると、明らかに狭そうで慌てて大きなケージに買い替えました。床材も金網から樹脂マットに変更。家族みんなで「もっと快適になったね」と話しあったのもよい思い出です。
また、一番の失敗だったのが、トイレの位置を頻繁に変えてしまったことです。最初は「もっと掃除しやすい場所に置こう」と思って、ケージ内のトイレを数日おきに移動していました。
すると、うちの子は混乱してしまったのか、ケージのあちこちでおしっこをするように…。このときは正直、私の判断ミスでした。そこで、「トイレの場所は固定する」「レイアウトは極力変えない」を徹底するようにしました。

この経験を通して感じたのは、子ウサギの成長に合わせて環境を整えてあげることの大切さです。見た目の可愛さや飼い主の都合だけでケージを整えるのではなく、ウサギにとって快適か、安全か、という視点を持つことが本当に重要なんですね。
いまでは、広いケージの中でのびのびと過ごす姿を見るたびに、「環境って大事だなぁ」としみじみ感じます。
4.愛情を注げば、ちゃんと伝わる:うちの子ウサギが人懐っこくなった理由
子ウサギが生まれたばかりの頃、「仲良くなれるのかな?」と少し不安でした。近づくだけで逃げられる日々。でも、「子ウサギのうちに愛情を注ぐと人懐っこく育つ」と本で読んで、できることから始めてみようと決めました。
毎朝「おはよう」と声をかけたり、名前を呼んだり。最初は耳をピクッと動かすだけだった「こむぎ」も、次第に顔をこちらに向けてくれるようになりました。
無理な抱っこはせず、おやつを手からあげたり、そばに座って静かに過ごす時間を大切に。撫でていても落ち着かない様子を見せたら、すぐにやめるようにしています。
そのうち「こむぎ」の方からそっと近づいてくれるように。今では足元でくつろぐ姿も見せてくれます。焦らず距離を縮めていけば、ちゃんと心は通じ合えるんだなと感じています。
5.子ウサギの成長って、本当にあっという間
「こむぎ」が生後1ヶ月を過ぎた頃、よく寝てよく食べ、ケージの中でぴょんぴょん跳ねている姿がなんとも可愛らしく、見ているだけで癒されていました。牧草に一生懸命かぶりつく姿に、小さな体でも力強く生きているんだなと感じたものです。
3ヶ月頃になると、食事のリズムが安定してきて、「もっとちょうだい」と催促されることも増え、成長していることを実感しました。部屋んぽでは、最初はおそるおそるだった「こむぎ」が、家具の隙間やカーテンの裏まで探検するようになり、行動範囲もどんどん広がっていきました。
性格も見えてきて、「こむぎ」は慎重で甘えん坊。新しいおもちゃには警戒心を見せるのに、おやつの時は我を忘れて突進してくるのが面白いです。
ただ、生後4~5ヶ月頃に突然の反抗期。トイレの失敗が増え、抱っこを嫌がる日もありました。「嫌われた?」と心配になりましたが、成長の一環と知って安心。昨日できなかったことが今日できるようになる、あっと言う間に成長します。その一つひとつの変化が嬉しくて、まるで子どもを育てているような毎日です。
6. まとめ:子ウサギとの暮らしは毎日が学び
「こむぎ」との毎日は発見と驚きの連続でした。最初は不安ばかりでしたが、そのたびに「次はこうしよう」と前向きになれました。小さな変化に気づくことで少しずつ自信がつきました。
これから子ウサギを迎える方へ。毎日の観察とスキンシップを大切に、焦らずゆっくりと信頼関係を築いてください。そうすれば、きっと最高のパートナーになりますよ。




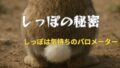

コメント