我が家のミニウサギ「みるく」を飼い始めた当初は、ペットショップで勧められたペレットを特に疑問も持たずに与えていました。しかし、みるくの体調や便の状態が安定せず、悩んでいたんです。
そんな時、ウサギの飼育について調べているうちに、ペレット選びが非常に重要であることを知りました。ペレットの種類や原材料、栄養バランスによって、ウサギの健康状態が大きく左右されることを知り、衝撃を受けました。
ペレットの種類や選び方のポイントを、私の体験談を交えながら、詳しくお話したいと思います。
1.ペレットの役割 :わが家の体験から
ウサギの食事はチモシー(牧草)が中心で、ペレットは副食という位置づけ。でもこの副食が、ウサギの健康をしっかり支えてくれる縁の下の力持ちだと、わが家では何度も感じてきました。
特に季節の変わり目や成長段階の変化、健康トラブル時など、ペレットの工夫が食事全体のバランスや体調の維持に大きな役割を果たしてくれました。
1-1.栄養バランスの調整
ペレットは牧草だけでは不足しがちなビタミン、ミネラル、タンパク質などを補う重要な存在。わが家のウサギたちも、普段はチモシー中心ですが、毎朝と夜に決まった量のペレットを与えています。
特に寒い季節などは、食欲が落ちがちな子もいるのですが、ペレットを先に食べて「よし元気だな」と確認できるのが習慣になっています。また、獣医さんにも「チモシー中心+ペレット少量のスタイルは理想的」と言っていただき、安心して続けています。
1-2.成長期の栄養サポート
生後6ヶ月頃までは骨格や筋肉がぐんぐん発達する大切な時期。うちでは「ちょこ」が子ウサギだった頃、成長期用のペレットをしっかり取り入れていました。当時はまだ噛む力も弱かったので、ペレットに少しぬるま湯を加えてふやかして与えていました。
この方法だとお腹にも優しく、消化もスムーズ。初めてペレットを食べた時の「ちょこ」の満足そうな顔は今でもよく覚えています。タンパク質やカルシウムが豊富な成長期用ペレットのおかげで、しっかりした骨格と筋肉がつき、健やかに育ってくれました。
1-3.高齢期の健康維持
ウサギの高齢期は7歳頃からと言われています。わが家の「みるく」も7歳を迎えてから、食が少し細くなったり、好き嫌いがはっきりしてきたように感じました。その頃からは、柔らかめのソフトタイプのペレットや、ハーブ入りで香りの良いペレットをいろいろ試すようになりました。
特に食欲が落ちた日には、香りの強いペレットを少しだけ与えると、「みるく」が鼻をひくひくさせてぱくっと食べはじめる場面も何度かありました。このとき改めて「ペレットの種類や形状を変えてみることで、食欲や栄養摂取を助けられるんだな」と実感。
高齢期こそ柔軟な工夫が大事だと感じた経験です。
1-4.特定の健康状態のサポート
肥満や尿路結石、毛球症など、特定の健康課題に対応した療法食ペレットもあります。
我が家でも「みるく」が毛球症になった際に、この療法食ペレットの力にとても助けられました。
当時は換毛期に抜け毛が多くなり、お腹に毛がたまって便の出が悪化。獣医さんに相談したところ、高繊維質で毛球排出をサポートする専用ペレットをすすめられました。
最初は心配でそっと与えてみましたが、「みるく」は予想以上に気に入って食べてくれて、数日後にはフンの状態も改善。元気に走り回る姿を見て、「ペレット選びひとつでこんなに変わるんだ」と実感しました。
この経験から、体調が不安な時や何か異変があった時は、自己判断せず獣医さんに相談し、適切なペレット選びをすることが大切だと心から感じています。
ペレットはただの「補助食品」ではなく、ウサギの健康を支える頼もしい存在。成長期から高齢期まで、そして体調不良時まで、ウサギの状態や年齢に応じて選び方や与え方を工夫することがとても大切だと、わが家の経験から強く感じています。
2. ペレットの種類:成長段階と身体の状態を考えて選ぶ
ウサギのペレットは、
2-1. 原材料による分類
①チモシーベース
高繊維質・低カロリーが特徴のチモシーベースのペレットは、成ウサギの健康維持にとても適したペレットです。わが家でも「みるく」が大人になってからは、チモシーベースのペレットを主食に取り入れるようになりました。
チモシーベースのペレットは、消化器官の健康維持や肥満防止に役立つだけでなく、噛むことで歯の伸びすぎを抑制してくれるのも大きなメリット。硬めの粒が多いため、しっかり噛んで食べる習慣が自然と身につき、不正咬合のリスクを軽減する効果も期待できます。
大人のウサギ(6ヶ月以上)には、チモシーベースのペレットが安心しておすすめできる選択肢だと、わが家の体験からも自信をもって言えます。
今、我が家のウサギたちが食べているのは、通販で買っている「

②アルファルファベース
アルファルファベースのペレットは、高タンパク・高カルシウムで栄養価がとても高いため、成長期のウサギ(生後6ヶ月頃まで)にぴったりなペレットです。
わが家でも「ちょこ」が子ウサギだった頃は、チモシー+アルファルファベースのペレットという組み合わせで育てていました。
子ウサギは骨や筋肉がぐんぐん成長する大切な時期。特に「ちょこ」はお迎えした当初はとても小柄で食も細めだったので、栄養価の高いペレットでしっかりサポートすることを意識していました。
その頃はまだ牧草の食べ方も練習中だったので、ペレットで不足分の栄養をしっかり補えていたと思います。
生後6ヶ月が近づく頃、獣医さんに「そろそろチモシーベースのペレットに徐々に切り替えていきましょう」と、アドバイスをもらいました。理由は、アルファルファのカルシウムが多すぎると尿路結石のリスクが出てくるためです。
最初は「ちょこ」がアルファルファの甘みやコクのある味に慣れていたせいか、チモシーベースのペレットにはあまり興味を示さず、ぷいっとそっぽを向く日もありました。
そこで、最初はアルファルファベースとチモシーベースを7:3くらいで混ぜて与え、徐々に割合を変えていきました。1〜2週間ほどで慣れてきて、今ではチモシーベースのペレットをちゃんと食べてくれるようになりました。
この経験を通じて私が感じたのは、アルファルファベースのペレットは成長期の栄養サポートに本当に役立つということ。でも、切り替え時期は慎重に、ウサギのペースに合わせて行うことが大切だということも強く学びました。
もし急に切り替えていたら、食べなくなってしまったり、体調を崩していたかもしれないと今は思います。
2-2.年齢・目的に合わせた分類
①グロース(成長期用)
グロース(成長期用)のペレットは、骨格や筋肉が急速に発達する生後6ヶ月頃までの子ウサギにとって欠かせないアイテム。この時期のウサギは、大人のウサギよりもはるかに多くの栄養素を必要とするため、グロースペレットはその成長をしっかりサポートしてくれます。
わが家の「みるく」を迎えた頃も、ペットショップのスタッフさんに「グロースペレットは成長期にとても大切なので、しっかり与えてくださいね」とアドバイスをいただきました。
グロースペレットは高タンパク質・高カルシウムで、骨や筋肉の発達を助ける栄養素がバランス良く配合されているのが大きな特徴。「みるく」も迎えた当初はまだ体が小さく、しっかり成長してほしい!という気持ちでグロースペレットを用意していました。
最初はペレットをそのまま与えてみたのですが、食べるのに少し苦戦している様子だったので、やはりぬるま湯でふやかして柔らかくして与える工夫をしました。するとすぐに慣れてくれて、ふやけたペレットを夢中になって食べてくれる姿がとても可愛かったのを覚えています。
その後、徐々に噛む力も強くなり、ポリポリと音を立てて食べられるように。この時期の食事がしっかりできたおかげで、「みるく」はしっかりとした骨格と筋肉がついた健康なウサギに成長してくれました。
グロースペレットはアルファルファを基本に作られていることが多く、甘みや香ばしい香りがするため、ウサギの嗜好性がとても高いのも特徴。実際に「みるく」も、チモシーよりもペレットの方を先に食べたがる時期がありました。
そのため、チモシーを先にケージに入れて食べさせる→あとでペレットを与えるという順番にして、牧草中心の食生活が身につくよう工夫しました。この頃の経験から、「嗜好性が高いからこそ量の管理が大事」ということも学びました。
好きだからといって食べ放題にすると栄養が偏ってしまうため、体重や食事全体のバランスを見ながら適量を守ることがとても重要です。
②メンテナンス(大人のウサギ用)
生後6ヶ月以降の大人のウサギに適したペレットが、メンテナンスタイプ。このペレットはチモシーベースで作られており、健康維持に必要な栄養素がバランスよく含まれています。
さらに、商品によっては関節の健康維持をサポートする成分(グルコサミンやコンドロイチンなど)が配合されているものもあり、年齢を重ねたウサギにも安心して与えられるのが特徴です。
今、わが家には3羽のウサギがいます。どの子もこのメンテナンスタイプのペレットが大好きで、毎回ペレットの袋を開ける音がするだけで、耳をピンと立ててケージの前に集まってきます。
我が家では朝と夜の2回に分けてペレットを与えるようにしているのですが、お皿に入れた途端に一斉に食べ始め、すぐに完食してしまいます。とくに末っ子の「くー」は食べ終わった後もお皿をじっと見つめたり、私のほうを見上げて「もっと欲しいよ」という目でアピール。
こちらもついつい甘やかしたくなってしまうのですが、健康維持のためには適量を守ることが大切だと獣医さんにも言われているので、そこはぐっと我慢。
その代わりに、ペレットを食べ終わったあとにはたっぷり撫でたり、一緒に遊んだりして気を紛らわせる時間を意識して作るようにしています。この時間が逆にウサギたちとのコミュニケーションタイムになっていて、今では私も毎回楽しみな時間になっています。
メンテナンスタイプのペレットはチモシーベースが基本なので、肥満防止や消化器官の健康維持にも安心。我が家でも何種類か試しましたが、香りや粒の大きさによって子たちの食いつきに差が出ることがありました。
最終的に今使っているペレットはみんながよく食べて、便の状態も安定しているものに落ち着きました。また、関節サポート成分入りのものも使っているので、年齢を重ねてからの体のケアにも役立っていると感じています。

③毛球ケア用
ウサギの毛球症とは、グルーミング中に飲み込んだ毛が胃腸内で詰まり、消化不良や食欲不振、便秘を引き起こす病気です。
放置すると症状が悪化し、最悪の場合は命に関わることもあると、獣医さんから聞いたときはとてもショックでした。
実際にわが家でも、7歳になる「みるく」が春の換毛期にごはんを残すようになったことがありました。大好きなチモシーにもあまり口をつけず、便の量も少なくてコロコロに。普段と明らかに違う様子に不安を感じ、すぐに動物病院を受診しました。
獣医師の診断は「毛球が原因で腸の動きが弱っている可能性がある」とのこと。その際に勧められたのが、繊維質が豊富で、毛球ケアに配慮したペレットでした。
毛球ケア対応のペレットには、
- 豊富な繊維質(主にチモシー由来)で腸の動きを活性化させ、毛の自然な排出を促す働き
- パパイヤ酵素やパイナップル酵素などの消化酵素で、毛球の形成を抑制し、胃腸の負担を減らす効果
が期待できます。
「みるく」には、まず1日2回、通常のペレットに1割ほど混ぜる形でスタート。香りがほんのり甘く、最初は警戒していたものの、数日で慣れ、喜んで食べてくれるようになりました。
すると、2〜3日後には便の量が増え、食欲も戻ってきたのです。この時の回復の速さには本当に驚きましたし、毛球ケアペレットの大切さを身をもって実感しました。
今では、換毛期前後には毛球ケア用のペレットを少しずつ混ぜて与えるのが習慣になりました。また、水分補給やブラッシングなどのケアと一緒に行うことで、「予防の一環」として毛球症にしっかり備えることができています。
④肥満ケア用
ウサギの肥満は、関節や内臓に大きな負担をかけるだけでなく、寿命にも影響するリスクのある状態です。見た目がふっくらしていても可愛いから…とつい見逃しがちですが、適正体重を保つことが健康維持にはとても重要だと私は実感しています。
実はうちの「ちび」も、6歳を過ぎた頃から少しずつ体重が増加してしまった時期がありました。特に冬の間は運動量が減り、気づけばお腹まわりがふっくら。抱っこしたときの重さも明らかに増していたので、動物病院で相談したところ「肥満予防用のペレットに切り替えてみましょう」とアドバイスを受けました。
肥満ケア用のペレットは、
- 低カロリー・高繊維質設計で、少量でも満腹感が得やすく、腸の動きもサポート
- 脂質・糖質の含有量が抑えられ、肥満のリスクを減らす
- 必要なビタミンやミネラルはしっかり配合されているため、栄養バランスは保たれる
という特徴があります。また、チモシーベースのものが主流なので、日常の食事に無理なく取り入れやすいのも良い点でした。
最初は「ちび」が今までのペレットから味の違いに気づいて食べなくなるのでは?と心配でしたが、意外にもすんなり受け入れてくれました。切り替え時は今までのペレットと肥満ケア用ペレットを半量ずつ混ぜてスタート。
徐々に割合を変えていき、2週間ほどで完全に肥満ケア用ペレットに移行できました。与え始めて1ヶ月ほど経つと、体重が少しずつ安定してきたのが分かりました。便の状態も良好で、本人もストレスなく元気に過ごしていたので安心しました。
今は体型も戻り、通常のメンテナンス用ペレットに戻していますが、換毛期など体重が増えやすい時期は肥満ケア用ペレットをうまく活用するようにしています。
2-3.形状による分類
| ハードタイプ |
|
| ソフトタイプ |
|
3. ペレットの選び方:原材料と添加物をチェック
3-1.年齢と健康状態
ウサギのペレットを選ぶとき、
3-2.原材料は牧草が主原料
原材料表示を確認し、牧草が主原料であることを確認しましょう。穀物類(トウモロコシ、小麦など)が原材料になっていると、
3-3.繊維質が多いもの
繊維質が豊富なものを選びましょう。繊維質は、消化器官の健康維持に役立ち、
3-4.添加物が入っていないもの
原材料表示をよく確認し、
3-5.獣医師のアドバイス
ペレット選びに困ったら、獣医師に相談しましょう。獣医師は、ウサギの健康状態や年齢に合わせて、
4. ペレットの与え方:適切な量と与え方が大切
 【適切な量】ペレットの与えすぎは、肥満や消化不良の原因となります。
【適切な量】ペレットの与えすぎは、肥満や消化不良の原因となります。
以前「ちび」が、
多めに与えると牧草の摂取量が減少することがあります。パッケージに記載されている量を参考に、
また、ウサギの体重や活動量に応じて、
【与える回数】1日2回に分けて与えましょう。朝と夕方に分けることで、消化器官への負担を軽減します。
【与える時間】毎日決まった時間に与えましょう。規則正しい食事は、ウサギの生活リズムを整え、
【牧草とのバランス】ペレットは補助食であり、主食は牧草です。常に新鮮な牧草が食べられるようにしておきましょう。牧草は、ウサギの消化器官の健康維持に大切です。
「みるく」は牧草が大好きで、いつも美味しそうに食べています。
【急な変更は避ける】ペレットの種類を変更する場合は、
ペレットの袋を開封後は、適切に保存しましょう。
5.まとめ
ペレットは「補助食品」!主食は牧草です。
ペレット選びは、ウサギへの愛情表現の一つだと思います。ウサギの健康を第一に考え、適切なペレットを選ぶことで、ウサギとの生活がより豊かになります。
この記事が、ウサギのペレット選びに悩んでいる飼い主さんの参考になれば嬉しいです。
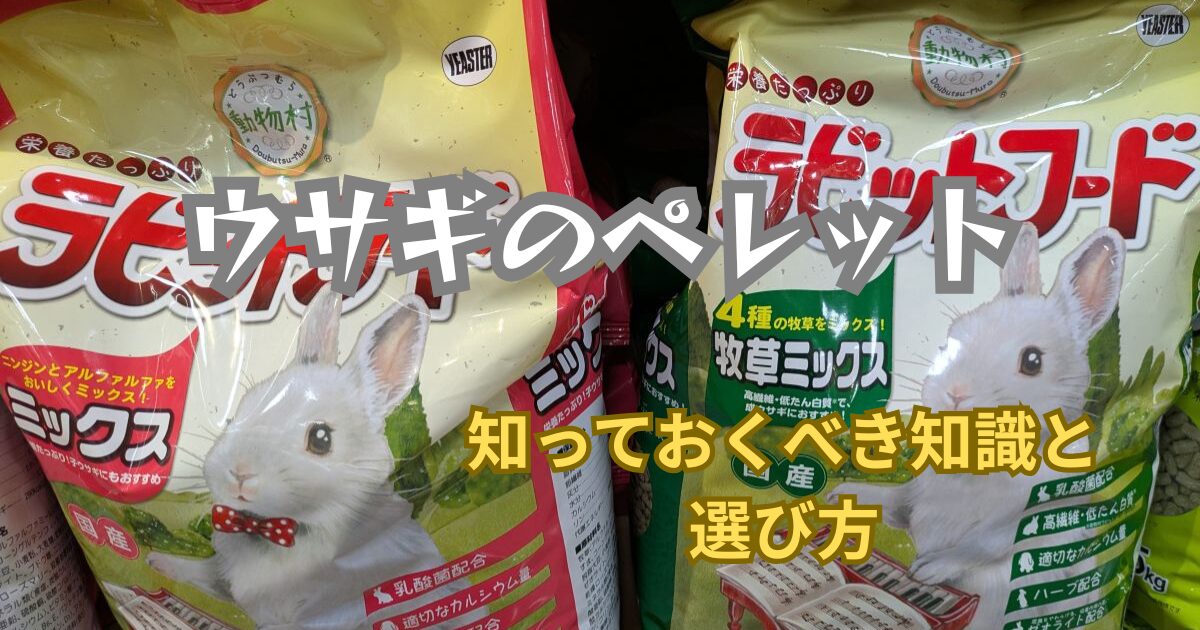


コメント