ウサギを健康に育てるうえで、もっとも大切な食べ物は「牧草」です。とくに主食となる「チモシー」は、歯や腸の健康、ストレス軽減にまで大きく関わってきます。
私の家でも、ネザーランドドワーフの「ちょこ」と暮らしていた経験から、「牧草をどれだけ食べてくれるか」が、ウサギの体調のバロメーターだと痛感してきました。
今回は、私の実体験をもとに、牧草の種類や選び方、注意点までくわしく解説します。ウサギを初めて飼う方、チモシーの食いつきに悩んでいる方にも、きっと役立つ内容です。
1.チモシーの特徴と種類
チモシーはウサギ飼育者にとって定番ですが。種類によって好みが分かれることがあります。我が家では「the First TIMOTHY」(通販サイトで購入)というチモシーを与えています。この商品は茎が太めで繊維質が豊富なので、消化器官にも良い影響があります。
特に1番刈りは嗜好性が高く、「ちょこ」をはじめ、どのウサギも夢中になって食べています。以前は他社製品も試しましたが、香りや硬さが合わず残してしまうこともありました。そのため、試行錯誤しながら最適な牧草を選ぶことが重要だと感じています。
1-1.チモシーの特徴
| 豊富な繊維質 | 消化器官の健康維持に役立ち、歯の伸びすぎを抑えます。 |
| 低タンパク・低カルシウム | 健康的な成長をサポートします。 |
| 嗜好性 | 多くの草食動物が好んで食べます。 |
| 種類 | 刈り取る時期によって、1番刈り、2番刈り、3番刈りなどがあり、それぞれ栄養価や食感が異なります。 |
1-2.チモシーの種類
1番刈り:太い茎、豊富な繊維質、嗜好性が高い
2番刈り:1番刈りに比べて葉が多く、柔らかい
3番刈り:葉が細かく、柔らかく、嗜好性が高い
2.チモシーが果たす大切な役割〜わが家のウサギたちとの暮らしから〜
2-1.「チモシーは主食」——飼いはじめて気づいた基本
我が家ののウサギたちにとって、チモシーはまさに「主食」と言える存在です。最初にウサギを飼い始めた頃は、「とりあえずペレットをあげていれば良いかな」と軽く考えていました。
そんな私に転機を与えてくれたのは、ペットショップの店員さんの一言でした。
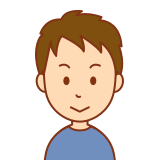
ウサギは草食動物なので、チモシーを主食にしてください。
とアドバイスをもらってから、毎日たっぷりとチモシーを用意するようになったのです。
我が家では1番刈りのチモシーから始めてみましたが、ウサギたちによっては2番刈りや3番刈りの方を好む子もいて、現在はそれぞれの子に合わせて複数の種類をブレンドしています。夢中でチモシーを食べている姿を見るたび、「この子たちはやっぱり草を食べる動物なんだ」と改めて実感します。
2-2. 腸内環境と健康のカギを握る繊維の力
換毛期になると、お腹の調子を崩しがちな子が一羽いました。いつもよりフンの様子が悪くなったので、すぐにかかりつけの動物病院で相談しました。
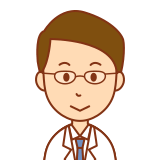
チモシーに含まれる繊維が腸の働きを助けてくれるので、しっかり食べさせてください。
そこで、フレッシュなチモシーをいつも以上にたっぷりと補充し、その子の好みに合ったものを工夫して与えてみたところ、数日でフンの状態が改善され、元気も戻ってきました。
この出来事をきっかけに、私は「腸の健康を守るためにチモシーは欠かせない」ということを身をもって学びました。それ以来、特に換毛期や季節の変化がある時期は、チモシーの量や鮮度に一層注意するようにしています。
2-3.チモシーが歯の健康を守る仕組み
ウサギの歯は一生伸び続けることを知ったとき、私はかなり驚きました。飼い始めた当初は、かじり木を入れておけば自然に削れるだろうと考えていたのですが、ある日、奥歯の伸びすぎで涙を流している子が出てしまいました。
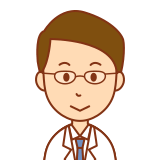
チモシーをよく噛むことで歯が自然に摩耗して、適切な長さを保てるんですよ。
と教えていただいたのです。
このことをきっかけに、チモシーの存在を「おやつ」ではなく「健康を支える基本の食材」として見直しました。以来、1日に何度か新しいチモシーを補充して常にフレッシュな状態をキープ。モグモグと夢中で食べている音を聞くたびに、「今日も健康に過ごせそうだな」と安心感を覚えるようになりました。
2-4.ストレス対策にも役立つチモシーの力
部屋んぽの時間になると、我が家のウサギたちはよく牧草の山に顔をうずめて、チモシーをかき分けながら楽しそうに過ごします。ある子は、茎の太さや香りを吟味して「お気に入り」だけを選んでポリポリ食べるのが日課になっています。
このような行動を見ていると、チモシーを噛む行為自体が精神的なリラックスやストレス解消につながっているのだと感じます。
特に印象的だったのは、引っ越しをしたとき。環境が変わってナーバスになっていた子が、チモシーを自由に食べられる環境を作ったことで徐々に落ち着きを取り戻したのです。
それ以来、環境の変化や体調の揺らぎが見られる時期には、チモシーの量を増やして心身のバランスを整えるサポートをしています。


市販されている牧草の大半はチモシーであることからも分かるように、これはウサギの健康維持に不可欠な食材です。ただ与えるだけでなく、ウサギの好みや体調、年齢に合った種類を選ぶことがとても重要です。
チモシーには、食事としての役割だけでなく、腸の調子を整え、歯の伸びすぎを防ぎ、さらに精神的な安定にもつながるという多面的な価値があります。
3. チモシー以外の牧草とその役割
3-1.オーツヘイ
オーツヘイは甘い香りが特徴で、「ちょこ」も大好きな牧草でした。ただし、一度与えすぎてしまった際、お腹の調子を崩したことがあります。それ以来、副食として少量ずつ与えるようにしていました。
また、オーツヘイは炭水化物や糖分が多めなので、成長期や体力回復時には良いですが、大人のウサギには控えめにする必要があります。この経験から、「嗜好性が高い=たくさん与えて良い」というというわけではないと学びました。
適切な量を守り、バランスの取れた食事を心がけましょう。
①オーツヘイの特徴
| 嗜好性の高さ | 穂の部分に自然な甘みがあり、チモシーに比べて嗜好性が高い傾向があります。牧草をあまり食べない動物にも好まれることがあります。 |
| 豊富な繊維質 | 消化器官の健康維持に役立ち、歯の伸びすぎを抑える効果があります。 |
| 栄養価 | チモシーに比べて炭水化物や糖分がやや多めです。成長期や体力回復が必要な場合に適しています。 |
②オーツヘイを与える際の注意点
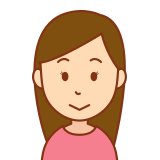
炭水化物や糖分が多いため、与えすぎると肥満の原因になることがあります。チモシーを主食とし、オーツヘイは副食として与えるのがおすすめです。
3-2.アルファルファ
アルファルファは、栄養価の高い牧草ですが、与え方には注意が必要です。
①アルファルファの特徴
高い栄養価:タンパク質、カルシウム、ビタミンなどが豊富です。成長期のウサギや、妊娠・授乳中のウサギに適しています。
嗜好性:多くのウサギが喜んで食べます。
注意点:カルシウムが多いため、成長したウサギに過剰に与えると尿路結石の原因になることがあります。高タンパク質のため、肥満にも注意が必要です。
|
成長期のウサギ
|
生後6ヶ月くらいまでの成長期のウサギには、積極的に与えても良いでしょう。 |
| 成長したウサギ | おやつ程度に少量を与えるのがおすすめです。イネ科のチモシーを主食とし、アルファルファは補助的に与えるようにしましょう。 |
| 妊娠・授乳中のウサギ | 妊娠中や授乳中のウサギは、多くの栄養を必要とするため、アルファルファを与えても良いでしょう。 |
②アルファルファはどう活用している?〜わが家の体験から〜
アルファルファは高タンパク・高カルシウムな牧草です。わが家でも生後6カ月頃までの子ウサギ時代は積極的に与えていました。特に成長期は身体作りに必要な栄養素が豊富なので、チモシーと併用しながらたっぷり食べさせたのをよく覚えています。
ただ、1羽が生後6カ月を過ぎた頃から尿の色が少し白っぽく濃くなることが増え、獣医さんから
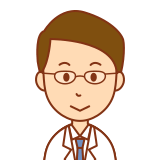
カルシウムの摂りすぎに注意してね
とアドバイスを受けました。
それをきっかけに、大人のウサギにはアルファルファを控えるように方針転換しました。
その後は特別な時だけのお楽しみとしてごく少量だけ与えるようにしています。一度、おやつ代わりにほんのひとつかみのアルファルファをあげたとき、ウサギたちは大喜び!
特に末っ子の子が「もっと欲しい!」と立ち上がっておねだりポーズをしてきた姿がとても印象的でした。
その時、「やはり嗜好性がとても高い牧草なんだな」と改めて実感。だからこそ大人のウサギには与える量をしっかり管理しなければと、今はおやつとして月に数回、ほんの一口分だけ特別なご褒美として活用しています。
こうした体験を通じて、アルファルファは栄養価の高さとリスクのバランスを意識しながら使うことがとても大切だと実感しています。
4. ウサギに牧草を与えるときのポイント
量の目安:ウサギの体重と同程度の量の牧草を、毎日与えましょう。牧草は食べ放題にして、
食べ残し:食べ残した牧草は、毎日取り除き、新しい牧草と交換します。
5.牧草を与える時の注意点
- 急な食事の変更 食事内容をいきなり変更すると、消化不良を起こす可能性があるため、
少しずつ切り替えます。 - 個体差 ウサギによって、好みや必要な栄養素が異なるため、
様子を見ながら調整します。 - 獣医師への相談 食事について不安な点や疑問点があれば、
獣医師に相談しましょう。 - オーツヘイやアルファルファは成長期のウサギにはいい牧草ですが、大人のウサギにはあまりよくありません。6か月ごろまではアルファルファ、それ以降はチモシーがよいですね。
- 牧草フィーダー
- 牧草フィーダーなどを使用すると、牧草が汚れにくく、
ウサギも食べやすくなります。
- 牧草フィーダーなどを使用すると、牧草が汚れにくく、
- 新鮮な水
- 常に新鮮な水が飲めるように、
給水ボトルやウォーターボウルを用意します。
- 常に新鮮な水が飲めるように、
- 野菜や果物
- 少量であれば、野菜や果物を与えることもできますが、
与えすぎは下痢の原因となるため、注意して与えましょう。
- 少量であれば、野菜や果物を与えることもできますが、
ウサギに与えて良い野菜や果物は、ウサギの健康を維持するために重要な要素です。しかし、与える際にはいくつかの注意点があります。
- 少量ずつ与える
- 野菜や果物は、あくまで副食として与え、主食である牧草を十分に食べさせることが重要です。
- 特に果物は糖分が多いので、少量ずつ与えるようにしましょう。
- 新鮮なものを与える
- 新鮮な野菜や果物を選び、よく洗ってから与えましょう。
- 傷んだものや腐りかけたものは、絶対に与えないでください。
- 徐々に与える
- 初めて与える野菜や果物は、少量から始め、便の状態などを確認しながら徐々に量を増やしていきましょう。
- 体質に合わない場合は、下痢などの原因になることがあります。
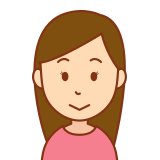
与えていい野菜・果物や、与えてはいけない野菜・果物はこちらでチェック
- ウサギの体調や年齢、個体差によって、適した野菜や果物は異なります。
- 不安な場合は、獣医師に相談することをおすすめします。
6.まとめ:牧草と共に築くウサギとの健やかな暮らし
「ちょこ」との暮らしを通じて、私は牧草の大切さを何度も思い知らされてきました。体調を崩したとき、牧草の見直しで元気を取り戻したこともあれば、誤った与え方でトラブルになったことも。
大切なのは、「その子に合った種類・量・状態の牧草を、毎日観察しながら与える」ことです。
このブログが、ウサギと暮らすあなたの毎日に、少しでも役立てば嬉しいです。



コメント