私がウサギと暮らし始めたのは、15年前の春。最初はその小さな手足や、ちょこんとした耳の動きに毎日癒されていました。しかし、月日が経つにつれ、愛兎「まろん」の食事の様子や動きに変化が現れ、飼い主として初めて心配や戸惑いを感じました。特にうまく「食べること」ができなくなった時の不安は、今も鮮明に覚えています。
この記事では、私の愛兎「まろん」が高齢期を迎えてから旅立つまでの“食”に関する介護体験をもとに、老ウサギと向き合う飼い主としての心がけや食事ケアの工夫を綴っていきます。
同じように介護に悩む方や、これから備えたいと思っている方のヒントになれば幸いです。
1.まろんの変化に気づいた日:小さなサインを見逃さずに
「まろん」が10歳を迎えた冬の朝、いつものように牧草を用意すると、以前なら飛びつくように食べていたのに、その日は牧草の前でじっと座ったまま動きませんでした。大好きなニンジンの葉を差し出しても、鼻先で軽く押し返すだけ。
普通なら「もっとちょうだい」と欲しそうにする仕草が見られず、私は胸がざわつきました。そして、3日続けて食べ残しが続いた時、初めて「これはただのきまぐれじゃない」と強く感じ、すぐに動物病院に連れて行きました。
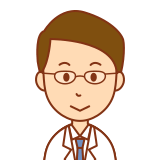
年齢に伴う歯のかみ合わせのズレと消化機能の低下です。病気ではないけれど、「まろん」はもう高齢期に入っています。
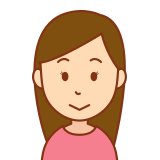
心の準備が必要だと感じました。
2.介護食のスタートは“無理なく少しずつ”
診断を受けたその日から、私は「まろんの今の体調に合った食事」を模索するようになりました。突然すべてを変えてしまうのではなく、「まろん」の様子を見ながら、段階的に介護食へとシフトしていきました。
診察を受けたその日、家に帰ってすぐ、「まろん」のペレットを40℃ほどのぬるま湯を加えて5分ほどふやかしてみました。最初は警戒して近づかなかったものの、指先で少しずつ口元に運ぶと、ゆっくりかみしめてくれました。
1粒ずつ、時間をかけて食べる姿に「これなら負担が少ないかもしれない」と希望が湧きました。ふやかすお湯の温度や、ペレットの柔らかさを毎回調整しながら、「まろん」の反応を観察する日々が続きました。
熱すぎないお湯でふやかし、香りを引き立てる程度の温度にするのがポイントです。食べ終わった後に、ぺろぺろと口をぬぐうしぐさが見られたときは、心からホッとしたのを覚えています。

3.食事は“楽しさ”も大切に
高齢期になると、ただでさえ体力も気力も落ちやすくなります。だからこそ、「栄養を取らせる」こと以上に、「まろんが食べることを楽しめるようにする」工夫を重視するようになりました。
ある日、乾燥ハーブのカモミールをほんの少しふやかしたペレットに混ぜてみたところ、「まろん」が鼻をクンクンさせて食いついたのです。その表情を見て、「食べることが楽しみになるようにしてあげたい」と強く思いました。
それからは、ある日は、乾燥パパイヤをひとつまみ、翌日はドライリンゴを小さく刻んで与えるなど、「まろん」の様子を見ながら毎日メニューを変えました。特に、ゆでた小松菜を初めてあげた時は、目を細めてゆっくりかみしめていたのが印象的でした。
「今日はどれが気に入るかな?」と私自身も楽しみながら食事を用意するようになりました。介護食でも、「嬉しい」「美味しい」と思える瞬間があるように工夫することが、「まろん」の意欲を引き出してくれたのです。
4.シリンジ食は“信頼の時間”
食事量が落ち込んできたある日、ついにシリンジによる強制給餌を検討することになりました。粉末状の栄養フードをお湯で溶き、1ccずつ口に入れるという方法です。
シリンジで口元に運ぶたび、「まろん」が一瞬だけ私の目を見つめる仕草がありました。最初は嫌がって首を振っていましたが、「大丈夫だよ、ゆっくりでいいからね」と声をかけると、しばらくして受け入れてくれるように。膝の上での給餌は、まるで「一緒に頑張ろう」と励まし合うような、特別な時間になりました。
「生きてほしい」という私の願いと、「まだ頑張るよ」というまろんの気持ちが交差する、特別な時間だったのです。

5.水分補給は“命の要”
「まろん」の体調が落ちてきた時期、水を飲む回数も減っていきました。高齢期には脱水が大きなリスクになります。
【水分補給のチェックポイント】
- おしっこの色が薄いがどうか
- 量が普段通りか
- 皮膚をつまんで、すぐに戻るか
この3点を毎日観察し、少しでも異変を感じたらすぐに対応するようにしていました。
また、私は以下のような方法で水分補給をサポートしていました。
- シリンジでこまめに給水(1回1~2ccを数回に分けて)
- ウェットな野菜(レタス・茹でた小松菜など)を取り入れるシリンジフードをやや水分多めに調整
ある日、「まろん」が突然ぐったりして動かなくなったときも、軽い脱水だったと分かり、早く気づいたことで命をつなげた経験もありました。

6.食べられない日も、ただ“そばにいる”
介護期の後半になると、どんなに頑張って工夫しても、どうしても食べてもらえない日が増えてきます。「まろん」も、まったく食べてくれない日が数日続き、体重が急激に減ってしまったことがありました。
私は不安で泣きたくなる気持ちになりながらも、無理に食べさせるのではなく、そっと「まろん」のそばに行って、優しく話しかける時間を増やしました。
「今日も生きてくれてありがとう」 「一口だけでも、えらいね」
そんな言葉をかけながら、目が合ったときに「まろん」が少し鼻を動かすだけで、涙が出るほど嬉しかったのを覚えています。
7.最後に:介護食は“愛情”のかたち
「まろん」は13歳の春、私の腕の中で静かに眠るように最期の時を迎えました。最後の数日は、ほとんど食べられなくなり、シリンジも受け付けない状態でしたが、ぴったり寄り添って過ごす時間が、私たちにとって何よりの癒しになっていました。
介護食は、単に栄養を与える手段ではありません。それは、飼い主からウサギへの「生きてほしい」「あなたが大切だよ」というメッセージを、毎日少しずつ形にして伝える手段でもあります。
「食べること」は「生きること」。まろんが私に教えてくれたその言葉の重みを、私はこれからもずっと忘れません。
もし、この記事を読んでいるあなたが、今まさに介護の真っ最中なら、無理をせず、焦らず、ただウサギさんの気持ちに寄り添ってください。そして、あなたの優しさが、きっとウサギの“生きる力”をそっと支えてくれるはずです。

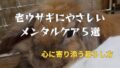
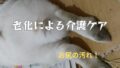
コメント