待ちに待った春の陽ざし!冬の間、おうちで過ごしていた愛らしいウサギと、そろそろ外の空気を楽しみたいと思っている、飼い主さんも多いのではないでしょうか?初めてのうさんぽにワクワクするけれど、何から始めればいいか不安…。
この記事では、初めてのうさんぽを安全に、そして飼い主さんもウサギも心から楽しめるように、準備から当日の注意点、帰りのお世話まで、私の体験談を交えながら詳しく解説します。
1.【安全第一】うさんぽに必須の持ち物リスト
安全第一でうさんぽを楽しむためには、しっかりと準備しておきたいグッズがあります。
①キャリー:ウサギ専用の安心空間
通気性が良く、ウサギが中で立ち上がって方向転換できる程度のサイズのキャリーを選びましょう。プラスチック製は丈夫でお手入れが簡単ですが、布製は軽量で持ち運びやすいのが特徴です。

②ハーネス:安全と快適性を両立
首輪タイプはウサギの首に負担がかかるため、必ずハーネスを選びましょう。体にフィットし、抜けにくい構造になっているかを確認してください。ハーネスになれたらリードも試してみましょう。
【体験談】「もふ」に初めてハーネスをつけた時、サイズが合わず抜け出しそうになりヒヤリとしました。その後、マジックテープとバックルで固定できるタイプを購入し、練習を重ねた結果、ハーネスを見るだけで散歩だと理解するようになりました。ウサギの体形に合わせた選び方が重要です。

③ウォーターボトル&容器:水分補給と緊急時の洗浄に
お散歩中の水分補給のために用意しましょう。また、万が一、コンクリートの上などでオシッコをしてしまった際に洗い流すのにも使えます。
給水方法の注意点:ノズルタイプに慣れていないウサギにはお皿タイプも用意しましょう。
【体験談】 夏場のうさんぽは特に水分補給が大切です。小型のウォーターボトルと、折りたたみ式のシリコン製容器を持ち歩いています。「もふ」も、休憩の度にゴクゴク飲んでくれます。
公園の水道が近くにない場合もあるので、予備の水も少し多めに持っていくと安心です。万が一、ハーネスが汚れてしまった時などにも使えます。
スプレーボトルに水を入れて持っていくと、暑い日にうさぎの体を軽く冷やしてあげることもできます。ただし、嫌がる場合は無理にかけないようにしています。
④もしもの時に!あると便利なもの
公園によっては、落ち葉などが多くてフンの掃除が大変な時があります。小さなほうきとちり取りがあると、サッと綺麗にできるので便利です。
ウェットティッシュは、うさんぽ中にちょっと手が汚れた時や、キャリーをしまう前に軽く拭いたりするのに役立ちます。意外と使用頻度が高いです。
2.うさんぽ成功のための徹底準備:場所選びの重要ポイント
何事も準備が大切。楽しいうさんぽを実現するために、事前にしっかりとリサーチを行なうことが大切です。
①場所選び:ウサギ目線で安全な環境を探す
【体験談】近所の公園で管理事務所に確認したところ、「ペットOK」でも除草剤が最近使用されたとのことで別の公園へ行きました。また、木陰が多く土の地面が広がる場所では、「もふ」が嬉しそうに穴掘りを試みたりして自然を満喫していました。こうした事前調査のおかげで安心して楽しめました。
春や秋でも、日差しが強い日は意外と暑くなります。木陰で休憩できる場所を見つけておくことは、ウサギの体調管理のためにとても重要だと感じました。
②水を汲める場所があると安心
【体験談】初めて土の地面に「もふ」を降ろした時、嬉しそうに地面をクンクン嗅いで、少しだけ穴を掘ろうとしていました。普段見られない行動が見られて、とても嬉しかったです。手を洗ったり、汚れたものを軽く洗い流したりするのに、公園の水道が近くにあると本当に助かります。飲み水とは別に、予備の水を持ち歩くようにしています。
③球技禁止、または球技エリアが区切られている場所を選ぶ
スケートボードやBMXなどができる場所も同様に、十分な距離が取れるか確認が必要です。
④カラスや野良猫など、ウサギを襲う可能性のある動物が少ないか確認
都会の公園でも、意外な場所に危険な動物が潜んでいることがあります。タヌキなども夜行性ですが、昼間に見かけることもあります。
⑤犬をノーリードで散歩させている人がいないか注意
犬はウサギを捕食する本能を持っている場合があります。ノーリードで自由に動き回る犬がいる場所では、安心してうさんぽを楽しむことはできません。
⑥付近の不審者情報や危険な生物情報を確認
大切なウサギを守るために、安全な場所を選ぶことが重要です。
【体験談】広々とした公園でも、時間帯によってはボール遊びをする子供たちがたくさんいることがあります。事前に様子を見て、安全な場所を選ぶように心がけています。
ある時、うさんぽ中にカラスが近くに降りてきたことがあり、「もふ」がとても怖がっていました。それ以来、なるべく開けた場所を選び、周囲を警戒するようにしています。
先日、うさんぽ中に、突然ノーリードの大型犬が近づいてきて、本当に怖い思いをしました。その後も同じようなことがあったので、その公園には行かなくなりました。飼い主としての責任をきちんと持ってほしいです。
また、近所の公園でセアカゴケグモが見つかったという情報があったので、しばらくうさんぽは見合わせることにしました。安全第一で考えたいと思います。
3.【体験談】うさんぽ中の心得:安全確保とマナーを守るための注意点
入念な下調べと準備を終えたら、いよいよ待ちに待ったうさんぽです。実際にウサギとお散歩する際に、特に注意しておきたい点を見ていきましょう。
①うさんぽ中は涼しい環境でリラックス
【体験談】夏場の日中は地面が熱くなるため、朝夕の涼しい時間帯にうさんぽをしています。一度、コンクリート上で「もふ」が足を上げて熱そうな様子を見せたことがあり、それ以来土の地面や木陰だけを選ぶようになりました。この経験からウサギ目線で環境を選ぶ重要性を学びました。
ただし、乾燥しすぎて土埃が舞うような場所も、ウサギの呼吸器に良くありません。できるだけ人通りの少ない、静かな場所が理想的です。
②地面に降ろす前に危険物がないか確認
ウサギを地面に降ろす前に、散歩予定の範囲を軽く歩いて、お菓子の袋やタバコの吸い殻、割れた瓶などの危険なものが落ちていないか確認し、見つけたら必ず取り除きましょう。
小さな公園でも、意外とタバコの吸い殻や空き缶などが落ちていることがあります。ウサギが誤って口にしないように、毎回必ずチェックするようにしています。
安全が確認できたら、ハーネスをしっかりと装着し、緩みがないか再度確認します。リードをハーネスに取り付けるタイプのものは、留め具がきちんと固定されているかを念入りにチェックしましょう。

③草は食べさせない方が無難
動物OKの公園は、多くの犬が出入りしている可能性があり、草に犬のオシッコなどがかかっているかもしれません。そのため、公園の草は安易に食べさせない方が安心です。
【体験談】ウサギは草を食べるイメージがありますが、公園の草には何が付着しているかわからないので、絶対に与えないようにしています。代わりに、普段食べている牧草や野菜を持参するようにしています。
④キャリーにはいつでも入れるように準備
ウサギが疲れたり、怖がったりした時にすぐに休めるよう、キャリーを近くに置いておきましょう。
【体験談】少し歩き疲れた様子の「もふ」をキャリーに入れたら、すぐに横になって休んでいました。安心できる場所があることは、本当に大切ですね。
⑤遊ばせている間は絶対にリードを離さない
うさんぽ中は、どんな状況でもリードを絶対に離してはいけません。どうしても両手を使う必要がある場合は、安全な場所にしっかりと繋いでおくことをお勧めします。
これは、ウサギが驚いて逃げてしまったり、他の動物に襲われたり、人に連れ去られたりする危険を防ぐためです。また、犬の散歩と同様に、リードをしっかり握っていることは飼い主としての最低限のマナーです。
【体験談】一瞬、他の飼い主さんと話し込んでしまった隙に、「もふ」が排水溝の近くに駆け寄ってしまい、ヒヤリとしました。本当に一瞬たりとも目を離してはいけないと痛感しました。
リードを離してしまった時のことを想像すると、本当にゾッとします。どんなに慣れた場所でも、絶対に油断しないようにしています。
大好きなおやつで気を引ける場合もありますが、興奮していたり、怖がっていたりすると、おやつに気づかないこともあります。もし、ウサギの姿が見えなくなるほど遠くまで逃げてしまった場合、一人で連れて行っていたら発見は非常に困難になる可能性があります。
そのため、できれば最初から二人以上でうさんぽに出かける方が安心です。幸いにも逃げられた経験はありませんが、もしもの時のために、いつも夫婦二人でうさんぽに行くようにしています。役割分担ができるので、安心感が違います。
具体的な捜索方法:近隣への声かけ、SNSでの情報共有、動物保護センターへの連絡
⑥触られたくない場合のスマートな断り方
公園で他の人に「可愛い!」と声をかけられ、触ろうとされることもあるかもしれません。しかし、まだうさんぽに慣れていないウサギや、人見知りをするウサギの場合、無理に触られるとストレスになってしまうことがあります。
かといって、ストレートに「触らないでください」と言うのは角が立つことも。そんな時は、「すみません、まだお散歩に慣れていなくて、驚くと引っ掻いたり噛んだりしてしまうかもしれないので…」といったように、ウサギの安全を理由にした言い訳をすると、相手も理解してくれることが多いでしょう。
【体験談】「可愛いですね!」と声をかけられるのは嬉しいのですが、触られそうになった時は、「臆病な子なので、まだ人に慣れていないんです」と優しくお断りするようにしています。
⑦お散歩が終わったら必ず後始末を
ウサギのフンはビニール袋などで回収し、持ち帰りましょう。コンクリートの上などでおしっこをしてしまった場合は、持ってきた水で洗い流します。自分たちの出したゴミは全て持ち帰り、公園をきれいに保つように心がけることが大切です。
【体験談】うさぎのフンは小さいですが、きちんと持ち帰るのがマナーだと思います。他の利用者の迷惑にならないように、気を付けています。
4.【アフターケア】うさんぽ後も大切!ウサギの疲労回復と健康チェック
楽しいうさんぽから帰ってきたら、ウサギに適切なケアをしてあげることが大切です。
①帰宅後のお手入れ、健康チェックも忘れずに
【体験談】うさんぽから戻った「もふ」は毛に葉っぱや小さな虫が付いていることがあります。その度にブラシングしながら確認し小さな虫は取り除いています。また、お気に入りのおやつ(ペレット数粒)で疲労回復のお礼をすると、とても満足そうな様子でした。このケアのおかげで翌日も元気いっぱいです。
②ケージに戻してゆっくり休ませる
外でたくさん遊んだ後は、ウサギも疲れているはずです。体をきれいにしたら、静かなケージに戻してゆっくりと休ませてあげることをお勧めします。

外での遊びで喉が渇いているかもしれないので、新鮮な水がいつでも飲めるように用意しておきます。
③うさんぽの日はそっと見守る
いつもと違う経験をしたウサギは、興奮していたり、疲れていたりするはずです。うさんぽから帰ってきた日は、あまり構いすぎずに、翌日までゆっくりと休ませてあげましょう。
うさんぽの後は、いつもよりぐっすり眠っている「もふ」を見ると、連れて行ってよかったなと思います。 帰宅後は、ケージの中で静かに過ごさせてあげるようにしています。
5.まとめ
うさんぽの時は、特に初めての場合は、事前準備をしっかりしてウサギに不安や危険を感じせないようにしましょう。そうして徐々に慣れていくと、うさんぽが待ち遠しくなります。ぜひあなたの愛するウサギとのうさんぽを楽しんでくださいね。
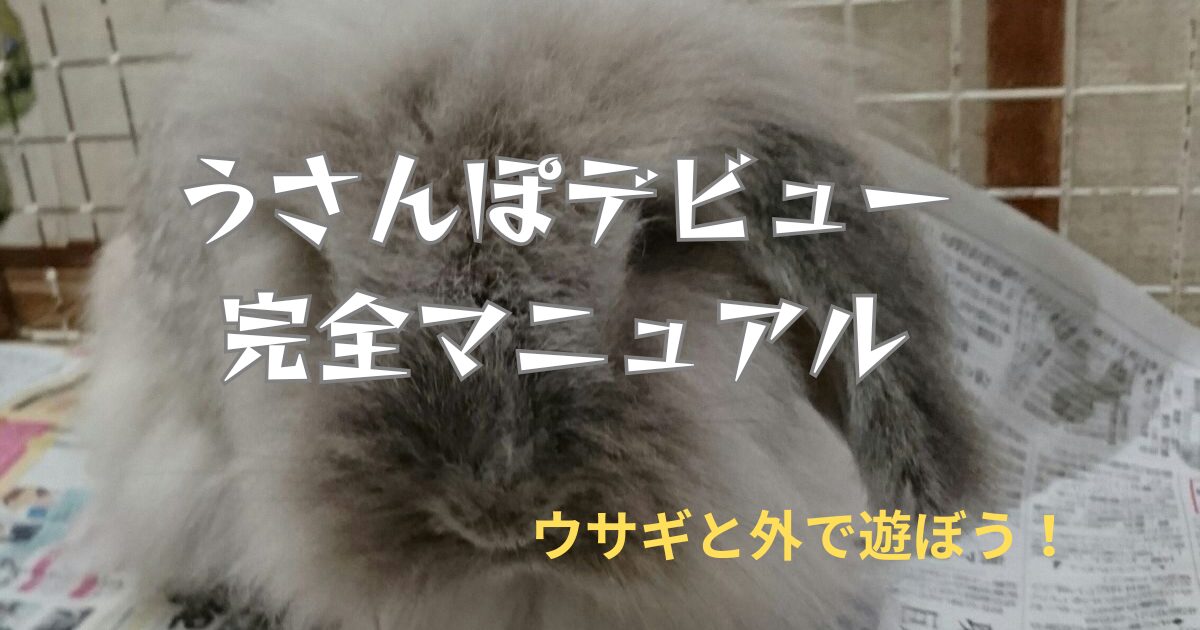


コメント